
「もしかして、我が家にもコウモリが?」そんな不安を感じて、ヘーベルハウスとコウモリの関係について調べているのではないでしょうか。
堅牢なイメージのあるヘーベルハウスですが、実はコウモリが住み着いてしまうケースは少なくありません。
その主な原因は、外壁の構造や経年によって生じるわずかな隙間にあります。
コウモリは1cm程度の小さな隙間があれば簡単に侵入してしまうため、対策を講じないと、糞尿による悪臭や建材の腐食、さらには健康被害といった深刻な問題に発展する可能性も否定できません。
この記事では、なぜヘーベルハウスにコウモリが住み着きやすいのか、その原因から具体的な対策、そして効果的な予防策までを網羅的に解説します。
ご自身でできる初期対応や早期発見の方法はもちろん、専門の駆除業者に依頼する場合の注意点、さらには新築時にハウスメーカーと相談すべきポイントや、外壁塗装が予防策として有効かどうかも詳しく掘り下げていきます。
複数の業者から見積もりを取る際の手間を省くための便利なサービスとして、タウンライフ家づくりのようなプラットフォームの活用法にも触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
なお、ハウスメーカー各社の資料・カタログはコチラから入手すると、無料&まとめて一括請求できるので比較検討がとてもカンタンで便利です。
- ヘーベルハウスにコウモリが住み着きやすい原因
- コウモリの具体的な侵入経路となる家の隙間
- コウモリの存在を早期発見するためのサイン
- 被害を放置した場合に起こりうるリスク
- 法律を守りながら個人でできる初期対策
- 信頼できるコウモリ駆除業者の選び方
- 新築時に検討すべきハウスメーカーのコウモリ対策
\300万円以上の差がつく/
複数社比較の相見積もりは
やらないと損!!
▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼
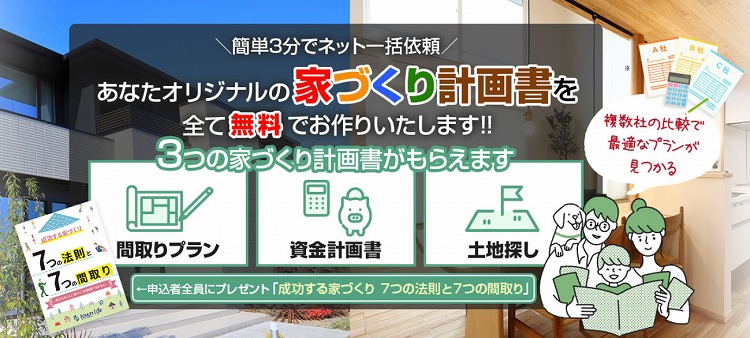 1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です
希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ
さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!
▼成功する家づくりプレゼント▼
- 希望の家の質問に回答(約3分)
- ハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
ヘーベルハウスのコウモリ被害、その原因は外壁にある?
- コウモリが住み着く家の構造的な原因
- ヘーベルハウスの外壁はコウモリを寄せ付けやすい?
- 1cmの隙間が侵入経路に!シャッターや換気口に注意
- コウモリがいるサインと早期発見のポイント
- 被害を放置すると健康被害のリスクも
コウモリが住み着く家の構造的な原因

戸建て住宅にコウモリが住み着いてしまう問題は、特定のハウスメーカーに限った話ではなく、家の構造そのものに起因するケースがほとんどです。
コウモリ、特に日本の家屋でよく見られるアブラコウモリ(イエコウモリ)は、非常に小さな体を持っており、わずか1cmから2cm程度の隙間さえあれば、いとも簡単に内部へと侵入してしまいます。
彼らが好むのは、雨風をしのげて、天敵から身を守れる安全で暖かい場所です。
そのため、住宅の屋根裏や壁の内部、軒下といった空間は、コウモリにとって絶好の繁殖・休息場所となり得ます。
具体的に、どのような構造がコウモリの侵入を許してしまうのでしょうか。
最も一般的な原因は、建材の接合部分に生じる隙間です。
例えば、屋根と壁の接合部、異なる外壁材が交わる部分、窓枠やドア枠と壁の間など、新築時には密閉されていても、経年劣化や地震の揺れなどによって、徐々に隙間が生まれることがあります。
また、換気口や通気口、エアコンの配管を壁に通すための穴の周りのシーリング(隙間を埋める充填剤)の劣化も、格好の侵入経路となります。
これらの場所は、設計上どうしても必要となる開口部ですが、メンテナンスを怠るとコウモリの侵入リスクを高める要因になるというわけです。
さらに、屋根の形状も関係しています。
複雑な形状の屋根は、シンプルな屋根に比べて接合部が多くなり、隙間が生まれやすくなる傾向にあります。
特に、瓦屋根の場合は瓦の重なり部分にわずかな空間ができるため、そこから侵入されるケースも報告されています。
これらの構造的な原因を理解することは、ヘーベルハウスに限らず、あらゆる戸建て住宅でコウモリ対策を考える上での第一歩と言えるでしょう。
家の構造を把握し、どこにリスクが潜んでいるかを知ることが、効果的な予防と駆除につながるのです。
ヘーベルハウスの外壁はコウモリを寄せ付けやすい?
ヘーベルハウスの最大の特徴は、ALCコンクリート「ヘーベル」を外壁に使用している点です。
この素材は、軽量でありながら高い断熱性、耐火性、遮音性を誇り、多くのオーナーから支持されています。
では、この特徴的な外壁が、コウモリの問題とどう関係してくるのでしょうか。
一部で「ヘーベルハウスの外壁はコウモリが住み着きやすい」という声が聞かれることがありますが、これはALCパネルそのものに問題があるわけではありません。
むしろ、問題はパネルの「目地」部分にあると考えられます。
ALCパネルは一枚一枚が大きいため、施工の際にはパネル同士を連結させることになります。
その連結部分、つまり目地は、柔軟性のあるシーリング材(コーキング)で埋められています。
このシーリング材は、地震の揺れを吸収したり、温度変化によるパネルの伸縮に対応したりする重要な役割を担っています。
しかし、シーリング材は紫外線や雨風にさらされることで、時間とともに劣化していきます。
劣化が進行すると、ひび割れや肉痩せ、剥がれといった現象が起こり、そこにわずかな隙間が生まれてしまうのです。
前述の通り、コウモリは1cm程度の隙間があれば侵入可能ですから、劣化した目地の隙間は、彼らにとって格好の入り口となり得ます。
また、ヘーベルハウスのデザインによっては、外壁に凹凸が多い場合もあります。
こうしたデザインは意匠性に優れていますが、凹凸部分や部材の取り合いが多くなるため、結果的に目地の総延長が長くなる傾向があります。
目地が多ければ多いほど、それだけ劣化による隙間が発生するリスク箇所も増えると言えるでしょう。
ただし、これはヘーベルハウスに限った話ではなく、シーリング材を使用する他の多くのハウスメーカーの住宅にも共通する課題です。
重要なのは、定期的なメンテナンス、特にシーリングの点検や打ち替えを計画的に行うことです。
適切なメンテナンスを施すことで、外壁の性能を維持し、コウモリの侵入リスクを大幅に低減させることが可能になります。
【関連】ヘーベルハウス公式
1cmの隙間が侵入経路に!シャッターや換気口に注意

コウモリの侵入経路は、前述した外壁の目地だけではありません。
私たちの住まいには、生活に欠かせない設備や機能を持たせるために、意図的に設けられた開口部や、構造上どうしても生じてしまう隙間が数多く存在します。
そして、それらの多くがコウモリの侵入経路となりうるのです。
ここでは、特に注意すべき具体的な場所をいくつか挙げてみましょう。
換気口・通気口
キッチン、浴室、トイレなどに設置されている換気扇のダクトや、建物の基礎部分にある通気口は、外部と直接つながっています。
通常はカバーや格子が取り付けられていますが、その網目が大きかったり、経年劣化で破損したりしていると、コウモリが侵入する可能性があります。
特に壁に設置された四角い形の換気口(ガラリ)は、羽をたためるコウモリにとって侵入しやすい構造になっている場合があります。
エアコンの配管穴
エアコンの室内機と室外機をつなぐ配管は、壁に穴を開けて通します。
施工後、その穴の周りはパテやシーリング材で埋められますが、この充填材が経年で硬化して縮んだり、剥がれたりすると隙間ができてしまいます。
この隙間も、コウモリの侵入経路として頻繁に指摘される場所です。
シャッターや雨戸の戸袋
窓に設置されたシャッターや雨戸を収納する戸袋の内部は、暗くて狭い空間であり、コウモリが好む環境です。
戸袋の上部や側面にわずかな隙間がある場合、そこから内部に侵入し、休息場所として利用することがあります。
毎日の開け閉めで気づきにくい場所だからこそ、注意が必要と言えるでしょう。
屋根と壁の隙間(軒下)
屋根の先端部分(軒先)と外壁が接する部分には、構造上、どうしても隙間ができやすいです。
「軒天」と呼ばれる軒の裏側の板がしっかり張られていない場合や、換気のための隙間が設けられている場合、そこが侵入経路となります。
特に、瓦屋根の波型の隙間は、コウモリにとって入りやすい形状をしています。
これらの場所は、いずれも1cm程度の隙間があればコウモリの侵入を許してしまいます。
定期的に自宅の周りを点検し、怪しい隙間がないか確認する習慣を持つことが、被害を未然に防ぐ上で非常に重要です。
コウモリがいるサインと早期発見のポイント
コウモリは夜行性で、人目につきにくい場所に巣を作るため、家に住み着いていても、その存在にすぐ気づくのは難しいかもしれません。
しかし、彼らが生活していれば、必ず何らかの痕跡(サイン)を残します。
被害が拡大する前に問題を察知するためには、これらのサインを見逃さないことが重要です。
早期発見のための具体的なポイントをいくつかご紹介します。
フン(糞)の発見
最も分かりやすいサインは、コウモリのフンです。
玄関先、ベランダ、窓の下、換気口の周辺など、特定の場所に黒くてパサパサした、長さ5mmから10mm程度のフンが落ちていたら要注意です。
ネズミのフンと似ていますが、コウモリのフンは昆虫を主食としているため、もろくて指でつまむと簡単に崩れるのが特徴です。
同じ場所にフンが集中して落ちている場合、その真上にコウモリの出入り口やねぐらがある可能性が非常に高いと考えられます。
夕方の飛来と早朝の帰巣
夕方、日没後の薄暗い時間帯(夏場であれば19時~20時頃)に、家の周りを飛び回るコウモリの姿を頻繁に見かけるようであれば、近くにねぐらがある可能性があります。
特に、特定の壁や屋根のあたりからコウモリが飛び立っていく様子が確認できれば、その建物に住み着いていることはほぼ間違いないでしょう。
逆に、明け方の薄明るい時間帯に、家に帰ってくるコウモリの姿を見ることもあります。
鳴き声や羽音
静かな夜、天井裏や壁の中から「キーキー」「チチチ」といった甲高い鳴き声や、ガサガサ、バタバタといった物音が聞こえることがあります。
コウモリの鳴き声は超音波が主であるため人間の耳には聞こえにくいことが多いですが、コミュニケーションのために可聴域の音を出すこともあります。
特に、巣に多くの個体がいる場合は、物音が聞こえやすくなります。
壁や柱のシミ
コウモリのフンや尿が同じ場所に長期間蓄積されると、天井や壁、柱などに黒っぽいシミができてくることがあります。
雨漏りと間違えやすいですが、特定の換気口や軒下周辺に原因不明のシミを見つけた場合は、コウモリの仕業を疑ってみる必要があります。
これらのサインに一つでも気づいたら、まずは懐中電灯などを使って、フンが落ちている場所の真上や、怪しい物音がする周辺を詳しく点検してみましょう。
早期発見・早期対応が、被害を最小限に食い止める鍵となります。
被害を放置すると健康被害のリスクも

「コウモリが家にいるかもしれないけれど、直接的な危害はないし、しばらく様子を見よう」と考えてしまうのは非常に危険です。
コウモリの存在を放置することは、建物そのものへのダメージだけでなく、そこに住む人間の健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があるからです。
具体的にどのようなリスクがあるのかを理解し、迅速な対応の必要性を認識することが大切です。
糞尿による建材の腐食と悪臭
コウモリは同じ場所にフンや尿を排泄する習性があります。
屋根裏や壁の内部に巣を作られると、大量の糞尿が断熱材や木材、天井板などに蓄積されていきます。
糞尿には酸性の成分が含まれているため、木材を腐食させたり、金属部分を錆びさせたりして、建物の耐久性を損なう原因となります。
また、湿気を含むことで強烈な悪臭を放ち始め、その臭いが室内にまで漂ってくることも少なくありません。
一度染み付いた臭いは、コウモリを駆除しただけでは消えず、大規模な清掃やリフォームが必要になるケースもあります。
害虫の発生源となる
コウモリのフンや死骸は、ダニやノミ、ゴキブリといった害虫の格好の栄養源となります。
コウモリの巣がある場所でこれらの害虫が大量発生し、そこから室内へと侵入してくることで、二次的な被害が拡大します。
特に、コウモリの体に寄生している「コウモリマルヒメダニ」や「コウモリトコジラミ」は、コウモリが巣を離れた後、新たな吸血源を求めて人を刺すことがあり、激しいかゆみやアレルギー症状を引き起こすことがあります。
感染症のリスク
コウモリは、さまざまな病原体(ウイルスや細菌)を保有している可能性があります。
直接コウモリに触れる機会は少ないかもしれませんが、乾燥したフンが粉末状になって空気中に飛散し、それを吸い込んでしまうことで、ヒストプラズマ症などの呼吸器系の感染症を引き起こすリスクが指摘されています。
また、海外では狂犬病ウイルスの媒介動物としても知られています。
日本の家屋に住み着くアブラコウモリから狂犬病が見つかった例は現在のところありませんが、野生動物である以上、素手で触ったり、安易に近づいたりすることは絶対に避けるべきです。
これらのリスクを考えると、コウモリのサインに気づいた時点で、できるだけ早く専門家へ相談し、適切な対策を講じることが、家族の健康と大切な住まいを守るために不可欠であると言えるでしょう。
\300万円以上の値引き実績あり!/
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
ヘーベルハウスのコウモリに有効な対策と今後の予防策
- 個人でできる初期対策と知っておくべき法律
- 信頼できる駆除業者の選び方と費用の目安
- 外壁塗装はコウモリ対策として有効なのか
- 新築時にできるハウスメーカーのコウモリ対策
- 無料一括見積もりならタウンライフ家づくり
- ヘーベルハウスのコウモリ対策は専門家への相談から
個人でできる初期対策と知っておくべき法律
自宅にコウモリがいると気づいたとき、「すぐに何とかしたい」と焦る気持ちはよく分かります。
しかし、ここで注意しなければならない重要な点があります。
それは、コウモリが「鳥獣保護管理法」という法律によって保護されているということです。
この法律により、許可なくコウモリを捕獲したり、殺傷したりすることは固く禁じられています。
違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
したがって、個人で行える対策は、コウモリを傷つけずに「追い出す」ことに限定されます。
法律を遵守した上で、個人でできる初期対策としては、以下のような方法が挙げられます。
忌避剤(きひざい)の使用
コウモリが嫌がるニオイを発するスプレーやジェル、錠剤タイプの忌避剤が市販されています。
ハッカ(ミント)やナフタレン系のニオイを嫌う性質を利用したものです。
コウモリの出入り口や巣がありそうな屋根裏、戸袋などに使用することで、コウモリを外へ追い出す効果が期待できます。
ただし、効果は一時的であり、ニオイが消えると戻ってきてしまう可能性が高いです。
また、屋根裏など広い空間全体に行き渡らせるのは難しいというデメリットもあります。
強い光を当てる
コウモリは夜行性で強い光を嫌います。
巣がありそうな場所に、懐中電灯やLEDライトなどで強い光を一定時間当て続けることで、居心地を悪くさせて追い出す方法です。
クリスマス用のイルミネーション(点滅するもの)なども効果的と言われています。
これも忌避剤と同様、根本的な解決にはならず、光を消せば戻ってくる可能性があります。
超音波発生装置
コウモリが嫌がる周波数の超音波を発生させる装置も市販されています。
一定の効果が報告されている一方で、コウモリがその音に慣れてしまうと効果が薄れるとも言われています。
また、障害物があると超音波が届きにくくなるため、設置場所を選ぶ必要があります。
これらの方法は、あくまで「追い出す」ための一時的な対策です。
最も重要なのは、コウモリを追い出した後に、侵入経路となっていた隙間を完全に塞ぐことです。
しかし、高所での作業や、すべての隙間を正確に特定して塞ぐ作業は、専門的な知識と技術がなければ非常に困難で危険を伴います。
そのため、個人での対策は初期対応に留め、根本的な解決は専門の駆除業者に依頼するのが最も安全かつ確実な方法と言えるでしょう。
信頼できる駆除業者の選び方と費用の目安
コウモリの駆除を専門業者に依頼することを決めたとき、次に問題となるのが「どの業者に頼めば良いのか」ということです。
残念ながら、害獣駆除の業界には、法外な料金を請求したり、不十分な施工を行ったりする悪質な業者も存在します。
大切な住まいと費用を無駄にしないためにも、信頼できる業者を慎重に選ぶ必要があります。
業者選びの際にチェックすべきポイントは以下の通りです。
- 現地調査と見積もりの丁寧さ: reputable業者は、必ず現地調査を行い、被害状況や建物の構造を詳細に確認した上で、作業内容と費用の内訳を明記した見積書を提出します。電話だけで金額を確定させたり、見積もりの内容が「一式」などと曖昧だったりする業者は避けるべきです。
- 実績と専門性: コウモリ駆除の実績が豊富かどうかを、ウェブサイトの施工事例などで確認しましょう。鳥獣保護管理法を遵守した施工方法をきちんと説明できるかどうかも、専門性を見極めるポイントです。
- 再発保証の有無: 信頼できる業者の多くは、施工後に再発した場合の保証制度を設けています。保証期間や内容を事前にしっかりと確認しておくことで、万が一の場合も安心です。
- 追加料金に関する説明: 見積もり以外の追加料金が発生する可能性があるかどうか、また、発生する場合はどのようなケースか、事前に明確な説明があるかを確認しましょう。「作業してみないと分からない」を多用する業者には注意が必要です。
駆除にかかる費用の目安ですが、これは被害の状況、建物の広さや構造、作業の難易度によって大きく変動します。
一般的には、追い出し作業と侵入経路の封鎖、糞の清掃・消毒を含めて、総額で100,000円~300,000円程度が相場と言われています。
ただし、屋根裏の断熱材を交換する必要があるなど、被害が甚大な場合は、それ以上の費用がかかることもあります。
費用を比較検討するためにも、必ず2~3社から相見積もりを取ることを強くお勧めします。
相見積もりを取ることで、料金の相場感が分かるだけでなく、各社の対応や提案内容を比較し、最も信頼できる業者を見つけることができます。
安さだけで選ぶのではなく、作業内容と費用のバランス、そして担当者の対応などを総合的に判断して、納得のいく業者を選びましょう。
外壁塗装はコウモリ対策として有効なのか

外壁のメンテナンスとして一般的な外壁塗装ですが、これがコウモリ対策としても有効なのか、疑問に思う方もいるでしょう。
結論から言うと、外壁塗装の工程に含まれる「下地処理」が、コウモリの侵入予防に非常に効果的です。
ただし、単に塗料を塗り替えるだけでは、根本的な対策にはなりません。
外壁塗装の基本的な工程は、「高圧洗浄」→「下地処理(ひび割れ補修やシーリングの打ち替え)」→「下塗り」→「中塗り」→「上塗り」という流れで進みます。
この中でコウモリ対策として最も重要なのが、「下地処理」の段階です。
ヘーベルハウスのようなALCパネルの外壁の場合、前述の通り、パネルの目地にあるシーリング材が経年劣化することで隙間が生まれ、コウモリの侵入経路となります。
外壁塗装を行う際には、この古くなったシーリング材を一度すべて撤去し、新しいシーリング材を充填する「打ち替え」という作業が行われます。
このシーリング打ち替えによって、劣化して生じた隙間が物理的に完全に塞がれるため、コウモリの侵入経路を断つことができるのです。
また、外壁に生じた細かなひび割れ(クラック)も、パテなどで丁寧に補修してから塗装を行います。
これにより、壁自体から侵入されるリスクも低減できます。
つまり、外壁塗装は、建物の美観を保ち、防水性能を回復させるだけでなく、害獣の侵入経路となりうる隙間を包括的にメンテナンスする絶好の機会となるわけです。
ただし、塗装業者を選ぶ際には注意が必要です。
業者によっては、シーリングの打ち替えを省略し、古いシーリングの上から新しいシーリングを重ねる「増し打ち」で済ませてしまうケースや、そもそも害獣対策の視点を持っていない場合もあります。
コウモリ対策を兼ねて外壁塗装を検討する際には、塗装業者に「コウモリの侵入を防ぎたい」という目的を明確に伝え、シーリングの打ち替えをしっかり行ってくれるか、小さな隙間も見逃さずに補修してくれるかを確認することが重要です。
害獣駆除の知識も持つ塗装業者であれば、より安心して任せることができるでしょう。
新築時にできるハウスメーカーのコウモリ対策
これから注文住宅を建てる、あるいは建て替えを検討している方にとっては、設計段階からコウモリ対策を織り込むことが、将来の安心につながる最も効果的な方法です。
「新築だから大丈夫」と油断せず、ハウスメーカーとの打ち合わせの際に、害獣対策、特にコウモリの侵入対策について具体的に相談することをお勧めします。
新築時に検討・依頼すべきコウモリ対策のポイントは以下の通りです。
侵入経路となりうる隙間を徹底的に塞ぐ
設計段階で、コウモリの侵入経路となりやすい箇所の対策を依頼しましょう。
- 換気口・通気口への防獣ネットの設置: 換気口や通気口の外部カバーの内側に、目の細かいステンレス製の金網(防獣ネット)などを設置してもらうことで、コウモリだけでなく、ネズミや昆虫の侵入も防ぐことができます。
- 配管周りのシーリング徹底: エアコンの配管や各種配線の引き込み口など、壁を貫通する部分の隙間は、耐久性の高いシーリング材で丁寧に埋めてもらうよう依頼します。
- 軒天や破風板の隙間対策: 屋根と壁の取り合い部分は、隙間ができないような納まり(施工方法)を検討してもらい、軒天ボードなどを確実に施工してもらいます。
コウモリが寄り付きにくい外壁材・構造の検討
外壁材の選定や家のデザインも、コウモリ対策に関わってきます。
例えば、外壁に凹凸が少なく、目地が少ないシンプルなデザインにすることは、コウモリが隠れたり、侵入したりするきっかけを減らすことにつながります。
また、シーリング材を使用しない外壁材(サイディングの四方合じゃくりなど)を選択することも一つの方法です。
ただし、デザイン性や他の性能との兼ね合いもあるため、ハウスメーカーの担当者とよく相談して決めることが重要です。
定期メンテナンス計画の確認
どんなに新築時に完璧な対策を施しても、経年劣化を完全に防ぐことはできません。
そのため、ハウスメーカーが提供している長期保証や定期点検のプログラム内容を確認し、シーリングの打ち替えなど、将来必要となるメンテナンスが計画に含まれているかを確認しておくことが大切です。
これらの対策を依頼することで、多少の追加費用が発生する可能性はありますが、後からコウモリ被害に遭い、駆除や修繕に高額な費用がかかることを考えれば、先行投資として非常に価値があると言えるでしょう。
無料一括見積もりならタウンライフ家づくり

注文住宅を建てる際、あるいは大規模なリフォームや外壁塗装を検討する際に、複数のハウスメーカーや工務店の情報を集め、比較検討することは非常に重要です。
コウモリ対策についても、各社がどのような標準仕様を持っているのか、どのような対策を提案してくれるのかは、会社によって異なります。
しかし、一社一社に個別に問い合わせ、資料を請求し、見積もりを依頼するのは、大変な手間と時間がかかります。
そこでおすすめしたいのが、「タウンライフ家づくり」のような無料の一括見積もり請求サービスです。
この種のサービスを利用するメリットは数多くあります。
自宅にいながら複数の会社を比較できる
最大のメリットは、住宅展示場に足を運んだり、個別の会社に何度も連絡を取ったりすることなく、一度の入力で複数の人気ハウスメーカーや工務店から、オリジナルの家づくり計画書(間取りプラン、資金計画、土地情報など)を取り寄せられる点です。
これにより、各社の特徴や費用感を効率的に比較検討することが可能になります。
希望や要望を伝えやすい
一括見積もりサービスの入力フォームには、要望を自由に記述できる欄が設けられていることがほとんどです。
ここに、「ヘーベルハウスのようなALC外壁を検討しているが、コウモリ対策について特に重視したい」「将来的なメンテナンス費用を抑えられるような害獣対策を提案してほしい」といった具体的な要望を書き込むことができます。
そうすることで、あなたの要望に沿った提案や見積もりを初期段階から受け取ることができ、その後の打ち合わせもスムーズに進められます。
客観的な視点で判断できる
営業担当者と直接対面すると、その場の雰囲気で判断してしまったり、断りにくくなったりすることがあります。
一括見積もりサービスなら、まずは取り寄せた資料やプランを自分のペースでじっくりと吟味し、客観的な視点で比較することができます。
その上で、気になった会社だけに絞って、次のステップに進むことができるのです。
ヘーベルハウスを含む多くの大手ハウスメーカーも、こうした一括見積もりサービスに参加しています。
コウモリ対策という具体的な課題を持って家づくりを検討している方にとって、各社の対応力を比較する上で、非常に有効なツールとなるでしょう。
利用は無料ですので、情報収集の第一歩として活用してみてはいかがでしょうか。
ヘーベルハウスのコウモリ対策は専門家への相談から
この記事を通じて、ヘーベルハウスとコウモリの問題について、その原因から具体的な対策、予防策までを多角的に解説してきました。
堅牢なヘーベルハウスであっても、外壁の目地の劣化など、経年によって生じるわずかな隙間がコウモリの侵入を許してしまう可能性があることをご理解いただけたかと思います。
そして、コウモリの被害は、放置すれば建物の損傷や健康被害といった深刻な事態につながりかねません。
もし、ご自宅でコウモリのサインに気づいたなら、まずは焦らず、この記事で紹介した情報を参考に状況を確認してみてください。
しかし、忘れてはならないのは、コウモリは鳥獣保護管理法で守られており、個人での駆除には限界と法的なリスクが伴うという点です。
最も安全かつ確実な解決策は、やはり専門の駆除業者に相談することです。
信頼できる業者であれば、法を遵守しつつ、コウモリを傷つけずに追い出し、侵入経路を確実に封鎖してくれます。
そして、糞の清掃や消毒まで含めて、衛生的な環境を取り戻すためのサポートをしてくれるでしょう。
また、これから家を建てる方やリフォームを検討している方は、設計段階や工事の計画段階で、ハウスメーカーや工務店、塗装業者にコウモリ対策の重要性を伝え、具体的な対策を講じてもらうことが、将来にわたる安心を手に入れるための鍵となります。
ヘーベルハウスのコウモリ問題は、決して他人事ではありません。
正しい知識を持ち、適切なタイミングで専門家の力を借りることが、あなたの大切な住まいと家族の健康を守るための最善の道と言えるでしょう。
- ヘーベルハウスでもコウモリ被害は発生しうる
- 主な原因は外壁ALCパネルの目地(シーリング)の劣化
- コウモリは1cm程度のわずかな隙間から侵入する
- 換気口や配管穴、シャッターの戸袋も侵入経路になる
- フンや鳴き声、夕方の飛来がコウモリ発見のサイン
- 被害の放置は建物の腐食や健康被害のリスクを高める
- コウモリは鳥獣保護管理法で保護されている
- 許可なく捕獲や殺傷をすると罰則の対象となる
- 個人でできる対策は忌避剤などでの「追い出し」のみ
- 根本的解決には専門業者による侵入経路の封鎖が不可欠
- 駆除業者は複数社から見積もりを取り慎重に選ぶべき
- 外壁塗装時のシーリング打ち替えは有効な予防策になる
- 新築時は設計段階でハウスメーカーに対策を依頼することが重要
- タウンライフ家づくり等のサービスで複数社の比較検討が効率的
- ヘーベルハウスのコウモリ対策は早期の専門家相談が最善策

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、
自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。
そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。
気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼
▼オリジナル間取りプランの例▼
『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓
- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい
- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い
- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい






















