
モデルハウスの購入を検討している人にとって、住宅ローン控除が適用されるかどうかは重要なポイントです。
新築扱いになるのか、それとも中古住宅として見なされるのかによって、控除期間や適用条件が異なるため、事前に確認しておく必要があります。
また、展示住宅ならではの注意点や、購入後に失敗しないためのポイントも押さえておくことが大切です。
住宅ローン控除を受けるには、建物の築年数や耐震基準の適合状況、ローンの返済期間など、さまざまな条件をクリアしなければなりません。
特に2025年以降の税制優遇制度では、省エネ基準が重視される傾向にあり、控除の適用を受けるためには条件が厳しくなる可能性があります。
これからマイホームを購入する人にとって、税制の変更を見据えた資金計画が求められます。
この記事では、モデルハウスを購入する際の住宅ローン控除の適用条件や、新築扱いになるかどうかの判断基準、税制優遇を最大限活用する方法について詳しく解説します。
住宅ローン控除を受けられる中古住宅の条件や、購入時に失敗しないための注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- モデルハウスが新築扱いになる条件がわかる
- 住宅ローン控除を受けるための具体的な条件が理解できる
- 中古住宅の住宅ローン控除が適用されるケースを知れる
- モデルハウス購入時の住宅ローン審査の注意点を学べる
- 2025年の税制優遇の変更点について知ることができる
- 展示住宅購入で失敗しないためのポイントがわかる
- 一括無料見積もりを活用するメリットを理解できる

ローコストで家を建てたいなら、
『タウンライフ家づくり』で気になるハウスメーカーを比較・検討してみませんか?
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の計画書を無料で提案してくれるので、あなたの予算と希望に合った最適なプランが見つかります。
\ 300万円以上の値引き実績あり! /
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
モデルハウスの購入で住宅ローン控除は受けられる?
- モデルハウスは新築扱いになる?適用条件を解説
- 中古住宅の住宅ローン控除は受けられる?適用範囲を確認
- 住宅ローン控除を受けるための具体的な条件とは?
- モデルハウス購入時に住宅ローンを組む際の注意点
- 2025年のマイホーム関連の税制優遇はどうなる?
モデルハウスは新築扱いになる?適用条件を解説

モデルハウスを購入する際に、多くの人が気にするのが「新築扱いになるのか?」という点です。
これは住宅ローン控除や税制優遇を受ける上で非常に重要なポイントとなります。
一般的に、新築住宅とは「建築工事が完了した日から1年以内で、かつ誰も住んでいない住宅」を指します。
しかし、モデルハウスは展示用として建てられており、一定期間、多くの見学者が出入りします。
そのため、新築として扱われるかどうかはケースバイケースとなります。
モデルハウスが新築扱いになる条件
モデルハウスが新築として扱われるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 建築工事の完了から1年以内であること
国土交通省の定義では、建築後1年以上が経過すると、中古住宅として扱われます。 - 居住履歴がないこと
モデルハウスは見学のために使われていますが、宿泊体験が可能な場合もあります。
宿泊者がいた履歴がある場合、新築として認められない可能性が高くなります。 - 登記上の所有者が変更されていないこと
住宅がすでにハウスメーカーや不動産会社名義で登記されている場合、新築扱いが難しくなります。
ただし、登記がなされていない場合は、新築住宅として扱われる可能性があります。 - 固定資産税評価額が新築基準であること
一部の自治体では、固定資産税の評価額を基準に新築・中古の区分を判断することがあります。
そのため、評価額の確認も重要です。
住宅ローン控除の適用条件
住宅ローン控除を受けるためには、新築住宅の定義を満たす必要があります。
しかし、モデルハウスは「中古住宅」として扱われることが多く、新築住宅としての控除を受けられない可能性があります。
以下の表で、新築・中古の住宅ローン控除の違いを確認しましょう。
| 項目 | 新築住宅 | モデルハウス(中古住宅扱い) |
|---|---|---|
| 住宅ローン控除期間 | 13年間 | 10年間 |
| 借入限度額(一般住宅) | 3,000万円 | 2,000万円 |
| 借入限度額(長期優良住宅) | 4,500万円 | 3,000万円 |
| 控除率 | 0.7% | 0.7% |
| 条件 | 建築後1年以内かつ未入居 | 一般的に建築後1年以上または見学履歴あり |
新築扱いにするための対策
もしモデルハウスを購入する場合、新築扱いを受けるために事前に確認すべきポイントがあります。
- 登記簿謄本の確認
物件の登記が行われていない場合、新築として購入できる可能性があります。 - 宿泊履歴の有無を確認
見学は問題ありませんが、宿泊体験が行われた場合、新築扱いが難しくなることがあります。 - 建築完了日を確認
契約時に建築完了日を確認し、1年以内であるかをチェックしましょう。 - 販売条件の確認
ハウスメーカーに、新築として扱われるかどうかを明確に確認し、契約書に記載してもらうと安心です。
モデルハウスは基本的に展示用の住宅であるため、新築住宅として扱われるケースは少なく、多くの場合、中古住宅とされます。
ただし、建築後1年以内であり、誰も住んでいない状態であれば、新築として購入できる可能性があります。
住宅ローン控除や税制優遇を最大限活用するためにも、事前に新築扱いの条件を確認し、ハウスメーカーや不動産会社としっかり相談しておくことが重要です。
中古住宅の住宅ローン控除の対象?適用範囲を確認

中古住宅を購入する際に、住宅ローン控除を適用できるかどうかは、多くの人が気にする重要なポイントです。
住宅ローン控除は、新築住宅に限らず、中古住宅を購入する場合でも適用されることがあります。
しかし、中古住宅には特有の条件があるため、事前にしっかりと確認しておくことが必要です。
ここでは、中古住宅が住宅ローン控除の対象となるケースと、その適用範囲について解説します。
中古住宅で住宅ローン控除を受けるための基本条件
中古住宅の購入でも住宅ローン控除を適用できるケースは、以下の基本条件を満たしている必要があります。
- 自己の居住用であること
住宅ローン控除は、購入者が実際に住むことを前提としています。
投資用物件やセカンドハウスでは適用されません。 - 床面積が50㎡以上であること
登記簿に記載された床面積が50㎡以上である必要があります。
ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けた物件で、合計所得が1,000万円以下の場合、40㎡以上でも適用されるケースがあります。 - 築年数の要件を満たしていること
中古住宅では、新耐震基準を満たしているかどうかが大きなポイントになります。
具体的には、以下の条件を満たしている必要があります。建物の構造 築年数要件 木造(耐火建築物以外) 築20年以内 鉄筋コンクリート造(耐火建築物) 築25年以内 もし、築年数が上記の基準を超えている場合でも、以下のいずれかの証明が取得できれば適用可能です。
- 新耐震基準適合証明書
- 既存住宅売買瑕疵保険の加入証明
- 住宅性能評価書(耐震等級1以上)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
住宅ローン控除は、ローンの返済期間が10年以上であることが条件となっています。
繰り上げ返済をして期間が10年未満になってしまうと、控除の適用が受けられなくなるため注意が必要です。
住宅ローン控除の適用範囲
住宅ローン控除の適用範囲は、新築住宅と中古住宅で若干異なります。
以下の表で、中古住宅の控除条件と新築住宅の違いを比較してみましょう。
| 項目 | 新築住宅 | 中古住宅 |
|---|---|---|
| 控除期間 | 13年間 | 10年間 |
| 借入限度額(一般住宅) | 3,000万円 | 2,000万円 |
| 借入限度額(長期優良住宅) | 4,500万円 | 3,000万円 |
| 控除率 | 0.7% | 0.7% |
| 必要な証明書 | 建築確認済証 | 新耐震基準適合証明書など |
中古住宅の住宅ローン控除は、新築住宅と比較すると控除期間や借入限度額が短く設定されています。
しかし、一定の条件を満たせば適用を受けられるため、購入前にしっかりと確認しておくことが重要です。
控除を受けるための手続き
中古住宅で住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
初年度は、以下の書類を準備し、税務署に提出する必要があります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 新耐震基準適合証明書(築年数要件を満たしていない場合)
2年目以降は、勤務先の年末調整時に「住宅借入金等特別控除証明書」と「年末残高証明書」を提出するだけで控除が適用されます。
中古住宅でも住宅ローン控除を適用できるケースはありますが、新築住宅とは異なり、築年数や耐震基準の条件を満たしているかどうかが重要なポイントとなります。
築年数の要件を超えている場合でも、新耐震基準適合証明書などを取得すれば適用される可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、控除期間や借入限度額は新築よりも短いため、資金計画をしっかりと立ててから購入を検討しましょう。
住宅ローン控除を受けるための具体的な条件とは?

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅購入者の税負担を軽減するための制度で、住宅ローンの年末残高の一定割合を所得税や住民税から控除できる仕組みです。
この制度を適用するためには、一定の条件を満たしている必要があります。
ここでは、住宅ローン控除の基本的な仕組みと、適用条件について詳しく解説します。
住宅ローン控除の基本的な仕組み
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して自宅を購入またはリフォームした際に適用される制度です。
年末時点の住宅ローン残高に応じて、一定額が所得税や住民税から控除されるため、住宅購入時の負担を軽減できます。
以下の表は、2025年時点での住宅ローン控除の基本的な適用内容です。
| 項目 | 2024年 | 2025年(予定) |
|---|---|---|
| 控除期間 | 13年(新築) | 継続予定 |
| 借入限度額(一般住宅) | 3,000万円 | 変更なし |
| 借入限度額(長期優良住宅) | 4,500万円 | 継続予定 |
| 控除率 | 0.7% | 継続予定 |
| 省エネ基準適合が必須 | 〇 | 〇 |
控除額は、住宅ローン残高の0.7%を上限として計算され、控除期間は新築住宅の場合13年、中古住宅やリフォームの場合は10年となるケースが多いです。
また、控除の対象となる住宅の種類や取得方法によって、借入限度額が異なる点にも注意が必要です。
住宅ローン控除を受けるための主な条件
住宅ローン控除を適用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
1. 自らが居住する住宅であること
住宅ローン控除は、購入した住宅が「自分が住むための家」であることが条件となります。
投資用の賃貸物件や、別荘・セカンドハウスとして利用する住宅は対象外です。
また、取得後6か月以内に入居し、その後も引き続き居住している必要があります。
2. 住宅の床面積が50㎡以上であること
住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅の床面積が50㎡以上である必要があります。
ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅については、所得が1,000万円以下の人に限り、40㎡以上でも適用可能です。
マンションなどの共同住宅の場合は、登記簿上の専有面積が50㎡以上であることが求められます。
3. 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
住宅ローン控除を受けるためには、ローンの返済期間が10年以上であることが条件です。
そのため、短期間で完済する計画を立てる場合は、控除の適用が受けられなくなる可能性があります。
また、繰り上げ返済を行い、結果的に返済期間が10年未満になった場合も、適用対象外となるため注意が必要です。
4. 年収が2,000万円以下であること
住宅ローン控除の適用を受けるためには、合計所得金額が2,000万円以下であることが条件となります。
この合計所得金額には、給与所得だけでなく、不動産所得や事業所得なども含まれます。
2025年時点でも、この基準が継続される見込みです。
5. 住宅の種類による適用条件の違い
住宅の種類によって、控除を受けられる借入限度額が異なります。
以下の表は、2025年時点の住宅の種類ごとの借入限度額を示しています。
| 住宅の種類 | 借入限度額 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
| 一般住宅(省エネ基準未達) | 0円(2024年以降適用外) |
2024年以降に建築確認を受けた新築住宅については、住宅ローン控除を適用するために「省エネ基準適合」が必須条件となりました。
そのため、これから住宅を購入する場合は、省エネ基準を満たす住宅を選ぶことが重要です。
6. 築年数の制限(中古住宅の場合)
中古住宅の購入でも住宅ローン控除は適用されますが、一定の築年数要件を満たしている必要があります。
具体的には以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
- 築年数が木造なら20年以内、鉄筋コンクリート造なら25年以内であること
- 耐震基準適合証明書が取得できること
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
築年数が基準を超えている場合でも、耐震基準を満たしていることが証明されれば、住宅ローン控除の対象になります。
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要です。
以下の書類を準備し、税務署に提出する必要があります。
- 確定申告書(初年度のみ)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 新築住宅の場合、省エネ基準適合を証明する書類
- 中古住宅の場合、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険証明書
2年目以降は、勤務先の年末調整時に「住宅借入金等特別控除証明書」と「年末残高証明書」を提出することで控除が適用されます。
住宅ローン控除を受けるためには、さまざまな条件を満たしている必要があります。
特に、新築住宅では省エネ基準適合が必須となり、中古住宅では築年数や耐震基準が重要なポイントになります。
また、住宅ローンの返済期間が10年以上であることや、合計所得金額が2,000万円以下であることも重要な条件です。
これから住宅を購入する方は、控除の適用条件を十分に理解し、最大限のメリットを活用できるように準備を進めましょう。
モデルハウス購入時に住宅ローンを組む際の注意点
モデルハウスを購入する際に住宅ローンを組むことは可能ですが、新築住宅や一般的な中古住宅と異なる点がいくつかあります。
モデルハウスは展示用として使用されていたため、金融機関によってはローン審査の基準が厳しくなることもあるため、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
また、住宅ローンの種類や税制優遇の適用条件も異なるため、注意が必要です。
ここでは、モデルハウスを購入する際に住宅ローンを組む際のポイントについて解説します。
モデルハウス購入の住宅ローン審査のポイント
モデルハウスの購入にあたっては、金融機関が住宅ローンを融資する際の審査基準が一般の新築住宅とは異なる場合があります。
以下の点を確認しておきましょう。
- 住宅の築年数の確認
住宅ローンの審査では、建物の築年数が大きなポイントになります。
一般的に「建築後1年以上経過した住宅」は中古住宅として扱われるため、新築住宅向けのローンが利用できない可能性があります。 - 固定資産税評価額のチェック
モデルハウスは展示目的で使用されていたため、建物の評価額が低めに設定されることがあります。
その結果、ローンの融資額が想定よりも低くなる可能性があるため、事前に金融機関と相談しておくことが重要です。 - 販売条件の確認
モデルハウスは通常の住宅とは異なり、家具や設備が付帯していることが多いです。
住宅ローンの対象となるのは「建物本体と土地」に限られるため、家具や家電の費用はローンに含まれないケースが多くなっています。
そのため、自己資金での支払いが必要になることを考慮しておきましょう。
住宅ローンの種類と適用範囲
モデルハウスの購入にあたり、利用できる住宅ローンには以下の種類があります。
| 住宅ローンの種類 | 利用の可否 | ポイント |
|---|---|---|
| フラット35 | 〇 | 一定の基準を満たせば利用可能 |
| 民間銀行の住宅ローン | 〇 | 金融機関ごとに審査基準が異なる |
| 新築住宅向けローン | △ | 建築から1年以上経過していると対象外 |
| 中古住宅向けローン | 〇 | 物件が中古扱いの場合はこちらを利用 |
一般的に、フラット35は築年数が古くても利用しやすい住宅ローンです。
また、銀行の住宅ローンについては金融機関によって審査基準が異なるため、事前に相談することをおすすめします。
頭金の準備と資金計画
モデルハウスを購入する場合、自己資金の準備も重要なポイントになります。
特に、以下の点を考慮して資金計画を立てましょう。
- ローンに含められない費用
モデルハウスの購入では、家具・家電、外構工事の追加費用などが発生することがあります。
これらの費用はローンの対象外になる場合があるため、事前に自己資金で対応できるように準備しておくことが大切です。 - 保証料や諸費用の確認
住宅ローンには保証料、登記費用、火災保険料などの諸費用が発生します。
これらの費用も自己資金で用意する必要があるため、物件価格だけでなく、総費用を考慮してローン計画を立てましょう。
モデルハウスの購入にあたって住宅ローンを組む際には、一般的な新築住宅や中古住宅とは異なる点がいくつかあるため、注意が必要です。
特に、築年数や固定資産税評価額、販売条件によってはローンの審査が厳しくなる場合があります。
また、家具や家電が付帯している場合、それらの費用は自己資金での支払いとなる可能性が高いため、事前に資金計画をしっかりと立てておくことが重要です。
住宅ローンの選択肢も複数あるため、フラット35や銀行のローンを比較し、自分に合った条件のローンを選ぶようにしましょう。
2025年のマイホーム関連の税制優遇まとめ

2025年のマイホーム関連の税制優遇制度について、最新の情報を確認しながら、住宅購入を検討している人が知っておくべきポイントを解説します。
2025年は住宅ローン控除や贈与税の非課税措置など、住宅購入に関わるさまざまな優遇制度が継続または変更される予定です。
制度を正しく理解し、最大限のメリットを受けられるように準備しましょう。
住宅ローン控除の変更点
住宅ローン控除は、住宅購入者の負担を軽減するための制度で、毎年の住宅ローン残高の一定割合が所得税や住民税から控除されます。
2025年も住宅ローン控除制度は継続される予定ですが、以下の点に注意が必要です。
| 項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 控除期間 | 13年(新築) | 継続予定 |
| 借入限度額(一般住宅) | 3,000万円 | 変更なし(予定) |
| 借入限度額(長期優良住宅) | 4,500万円 | 継続予定 |
| 控除率 | 0.7% | 継続予定 |
| 省エネ基準適合が必須 | 〇 | 〇 |
現在のところ、2025年の住宅ローン控除については大きな変更はないと予測されていますが、引き続き「省エネ基準を満たす住宅」であることが適用条件となる可能性が高いです。
そのため、省エネ性能の高い住宅を選ぶことが、控除額の最大化につながるでしょう。
贈与税の非課税枠の延長
親や祖父母から住宅取得資金を贈与してもらう際に適用される「住宅取得資金贈与の非課税措置」についても、2025年まで延長される予定です。
現在の非課税枠は以下の通りです。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 一般住宅 | 500万円 |
| 長期優良住宅・ZEH住宅 | 1,000万円 |
2025年もこの制度が維持される場合、親や祖父母からの資金援助を受けやすくなり、自己資金を増やして住宅購入が可能になります。
また、長期優良住宅やZEH住宅は非課税枠が大きいため、環境性能の高い住宅を選ぶことで税制優遇を受けやすくなります。
2025年のマイホーム関連の税制優遇制度は、住宅ローン控除や住宅取得資金贈与の非課税措置が継続される見込みですが、一部条件が厳格化される可能性もあります。
特に、省エネ基準の適用が引き続き求められるため、これから住宅を購入する場合は、環境性能の高い住宅を選ぶことがメリットとなります。
最新の税制改正情報を確認しながら、最大限の優遇を受けられるように準備を進めましょう。
\300万円以上の値引き実績あり!/
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
モデルハウスの購入で後悔しないためのポイント
- モデルハウスの購入で失敗しがちなケースとは?
- 展示住宅の住宅ローンに関する注意点
- モデルハウスの購入はお得?建売や注文住宅との違い
- 一括無料見積もりで住宅購入を有利に進める方法
- モデルハウスの購入前にやるべき資金計画とは?
- モデルハウスの購入で住宅ローン控除を受けるための重要ポイント
モデルハウスの購入で失敗しがちなケース【事例紹介】

モデルハウスの購入は、新築住宅と比べて価格が抑えられるメリットがありますが、購入後に後悔するケースも少なくありません。
展示用として建てられた住宅であるため、通常の住宅と異なる仕様やリスクが存在することを理解した上で慎重に判断する必要があります。
ここでは、モデルハウス購入でよくある失敗事例と、それを防ぐためのポイントを解説します。
1. 予想外の修繕費が発生した
モデルハウスは展示目的で使用されており、多くの見学者が訪れます。
そのため、床や壁に細かい傷がついていたり、ドアや窓の開閉がスムーズでなかったりすることがあります。
さらに、モデルハウスの使用期間が長い場合、設備や配管が劣化している可能性もあります。
購入後に補修が必要になり、予想外の修繕費が発生することがあります。
対策:
購入前に住宅診断(ホームインスペクション)を依頼し、建物の状態を細かくチェックしましょう。
また、売主であるハウスメーカーに修繕が必要な箇所を事前に確認し、購入前に補修してもらえるか交渉するのも有効です。
2. 住宅ローンの適用条件を確認せずに購入した
モデルハウスは「新築」として扱われるケースと「中古住宅」として扱われるケースがあります。
建築から1年以上経過している場合や、展示期間中に宿泊体験などで使用されていた場合は「中古住宅」と見なされ、住宅ローン控除の適用が受けられないことがあります。
対策:
購入前に、登記簿謄本で建築年月日を確認し、新築扱いになるかをチェックしましょう。
また、住宅ローン控除の適用条件を事前に税務署や金融機関に相談することをおすすめします。
3. モデルハウス特有の間取りや仕様が使いにくかった
モデルハウスは、見学者に住宅の魅力をアピールするために設計されています。
そのため、実際の生活では使い勝手が悪い間取りになっていることがあります。
例えば、吹き抜けのリビングや大きな窓が開放感を演出している一方で、冷暖房の効率が悪くなる場合があります。
対策:
購入前に、モデルハウスの間取りが自分のライフスタイルに合っているかどうかを慎重に検討しましょう。
実際に生活したときの動線をイメージし、収納スペースや家事のしやすさなども確認することが重要です。
4. 立地が希望に合わなかった
分譲地に建てられたモデルハウスは、すでに土地が決まっているため、自分で好きな場所を選ぶことができません。
購入後に「通勤・通学が不便だった」「周辺の環境が思ったより騒がしかった」などの理由で後悔するケースがあります。
対策:
事前に周辺環境をチェックし、昼夜の騒音や治安、スーパーや病院の距離などを確認しましょう。
また、将来的な土地の価値を考慮することも大切です。
モデルハウスの購入には多くのメリットがありますが、失敗しがちなポイントを理解しておくことが重要です。
住宅の状態やローンの適用条件、間取りの使いやすさ、立地などをしっかりと確認し、後悔しない住まい選びをしましょう。
展示住宅の住宅ローンに関する注意点
展示住宅(モデルハウス)を購入する際には、住宅ローンに関する注意点を理解しておくことが重要です。
一般的な新築住宅とは異なり、モデルハウスは特有の条件があるため、ローン審査の基準や適用できる控除が異なる場合があります。
ここでは、展示住宅の住宅ローンを利用する際の注意点を解説します。
1. 新築ローンが適用されるか確認する
モデルハウスは、新築として販売される場合と中古住宅として扱われる場合があります。
新築住宅向けの住宅ローンが適用されるかどうかは、建築年月日や居住履歴によって変わります。
対策:
事前に金融機関に相談し、新築ローンが利用できるかどうかを確認しましょう。
新築ローンが適用されない場合は、中古住宅向けのローンを検討する必要があります。
2. 借入額が希望通りにならない場合がある
モデルハウスは展示用のため、建物の固定資産評価額が低めに設定されていることがあります。
その結果、金融機関の評価額が想定よりも低くなり、希望額の融資を受けられないケースがあります。
対策:
複数の金融機関で事前審査を受け、どの程度の融資が可能か確認しておきましょう。
また、頭金を多めに用意することで、希望額に近づけることができます。
3. モデルハウス特有の設備費用が含まれる場合がある
モデルハウスは、家具や家電、カーテン、照明などが備え付けられていることが多いです。
しかし、これらの設備は住宅ローンの融資対象にならないケースが多く、別途自己資金での支払いが必要になります。
対策:
契約時に、どの設備が購入価格に含まれるのかを明確に確認し、資金計画を立てましょう。
展示住宅の住宅ローンには、新築か中古かの判断、借入額、設備費用の扱いなど、通常の住宅購入とは異なる点が多くあります。
事前に金融機関と相談し、適用されるローンの種類や条件を確認することで、スムーズに購入手続きを進めることができます。
モデルハウスの購入はお得?建売や注文住宅との違い
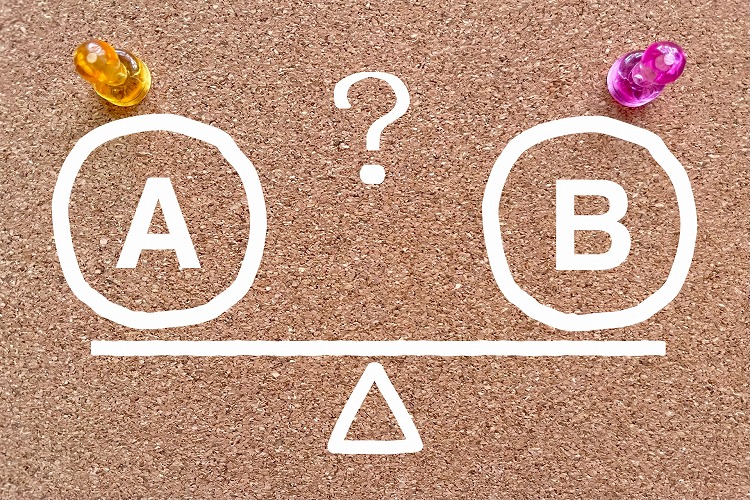
モデルハウスの購入は、一見すると価格が安く、設備が充実しているためお得に感じるかもしれません。
しかし、建売住宅や注文住宅と比較すると、それぞれに異なる特徴があります。
ここでは、モデルハウス・建売住宅・注文住宅の違いを詳しく解説し、自分に最適な選択肢を見つけるためのポイントを紹介します。
モデルハウス・建売住宅・注文住宅の比較
| 項目 | モデルハウス | 建売住宅 | 注文住宅 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 割安(値引き交渉可能) | 比較的安価 | 高め |
| 間取り | 展示用でおしゃれだが実用性に欠けることも | 一般的な間取り | 自由に設計可能 |
| 設備 | 最新の設備が導入されていることが多い | 標準的な設備 | 好きな設備を選べる |
| 購入時の状態 | 完成済み・即入居可能 | 完成済み・即入居可能 | 建築期間が必要 |
| 住宅ローン | 新築扱いとならない可能性あり | 新築ローン利用可能 | 新築ローン利用可能 |
モデルハウスの購入は、価格面や設備面でのメリットがあるものの、住宅ローンの適用条件や間取りの実用性に注意が必要です。
建売住宅や注文住宅と比較し、それぞれの特徴を理解した上で、自分のライフスタイルに最適な住宅を選ぶことが大切です。
一括無料見積もりで住宅購入を有利に進める方法

住宅を購入する際、価格や条件を比較せずに決めてしまうと、後から「もっとお得な選択肢があったのではないか」と後悔する可能性があります。
特にモデルハウスの購入を検討している場合、ハウスメーカーごとの価格や仕様をしっかり比較することが重要です。
ここでは、一括無料見積もりを活用することで、より有利に住宅を購入する方法を解説します。
1. 一括無料見積もりとは?
一括無料見積もりとは、複数のハウスメーカーや工務店に対し、同時に住宅の見積もりを依頼できるサービスのことです。
例えば「タウンライフ家づくり」などがあります。
通常、個別にハウスメーカーを訪問し、見積もりを取ると、1社ごとに時間がかかり、比較が難しくなります。
しかし、一括無料見積もりを利用することで、短時間で複数の業者の価格やプランを比較できるため、効率的に最適な住宅を見つけることができます。
2. 一括無料見積もりを利用するメリット
- 価格の比較が容易
住宅購入では、同じような仕様の住宅であっても、ハウスメーカーごとに価格が異なります。
一括見積もりを利用すると、各社の価格を一覧で比較できるため、よりコストパフォーマンスの良い住宅を選ぶことができます。 - 交渉材料として活用できる
価格や仕様を事前に把握することで、ハウスメーカーとの交渉がしやすくなります。
「他社ではこの価格で提供している」という情報があると、値引き交渉もしやすくなります。 - 時間と手間を削減できる
住宅展示場を訪れると、1社あたりの見学や打ち合わせで数時間かかることもあります。
一括見積もりを活用すれば、自宅で複数の見積もりを比較できるため、時間と手間を大幅に削減できます。 - 住宅ローンの借入額を適正に設定できる
事前に見積もりを取ることで、どの程度の予算が必要かを明確にできるため、無理のない資金計画を立てやすくなります。
3. 一括無料見積もりを利用する際の注意点
- 見積もりの内容を細かくチェックする
価格だけでなく、含まれている設備や仕様を確認することが大切です。
同じ価格帯の住宅でも、標準仕様に含まれる設備が異なるため、細かい部分まで比較しましょう。 - 過剰な営業に注意する
一括見積もりを利用すると、ハウスメーカーから営業の連絡が入ることがあります。
必要のない会社は丁寧に断り、自分に合ったメーカーに絞り込むことが大切です。 - 信用できるサイトを利用する
一括見積もりのサービスは数多くありますが、中には信頼性の低いものもあります。
利用者の口コミや実績を確認し、信頼できるサイトを選ぶようにしましょう。
一括無料見積もりを利用することで、効率的に最適な住宅を見つけることができます。
価格や仕様を比較することで、無駄な出費を抑えつつ、納得のいく住宅購入が可能になります。
特にモデルハウスを購入する場合は、新築住宅との価格差や設備の違いを考慮しながら、最適なプランを選ぶことが重要です。
モデルハウスの購入前にやるべき資金計画とは?
モデルハウスの購入を検討する際、事前にしっかりとした資金計画を立てることが重要です。
住宅は一生に一度の大きな買い物となるため、無理のない予算を設定し、将来のライフプランを見据えた計画を立てることが必要です。
ここでは、モデルハウス購入前にやるべき資金計画のポイントを解説します。
1. 総予算を明確にする
住宅購入にかかる費用は、物件価格だけではありません。
以下のような諸費用も発生するため、総予算を明確にすることが大切です。
| 項目 | 目安の費用割合 |
|---|---|
| 物件価格(本体価格) | 約80% |
| 登記費用・手数料 | 約5% |
| 住宅ローン手数料・保証料 | 約3% |
| 火災保険・地震保険 | 約2% |
| 修繕・リフォーム費用 | 約10% |
モデルハウスは展示用に建てられたため、細かい傷や設備の劣化がある可能性があり、修繕費がかかることがあります。
これらの費用も含めて、総予算を計算しましょう。
2. 住宅ローンの借入可能額を確認する
住宅ローンの借入額は、年収や借入期間によって決まります。
一般的に、年収の25%以内の年間返済額に収めるのが理想とされています。
借入可能額を確認することで、無理のない返済計画を立てることができます。
3. 頭金をどの程度用意するか決める
頭金を多く用意すると、借入額を抑えることができ、毎月の返済負担を軽減できます。
ただし、貯金をすべて頭金に充ててしまうと、突発的な支出に対応できなくなるため、生活費の6か月分は手元に残しておくのが理想です。
4. 住宅ローン控除や税制優遇を活用する
モデルハウスの購入でも住宅ローン控除を受けられる場合があります。
新築として認められるか、中古扱いになるかによって、控除額や適用期間が異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、2025年の住宅取得資金贈与の非課税措置も活用できる可能性があるため、親族からの資金援助を検討している場合は、適用条件を確認しましょう。
モデルハウスの購入前には、物件価格だけでなく、諸費用や修繕費用、住宅ローンの借入可能額などを考慮した資金計画が必要です。
無理のない返済プランを立て、住宅ローン控除や税制優遇を最大限活用することで、安心して購入を進めることができます。
モデルハウスの購入で住宅ローン控除を受けるための重要ポイント

モデルハウスを購入する際、住宅ローン控除を適用できるかどうかは重要なポイントです。
控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減し、長期的に経済的なメリットを享受できます。
しかし、モデルハウスは「新築扱い」となる場合と「中古住宅扱い」となる場合があり、それによって控除の条件が異なります。
ここでは、住宅ローン控除を受けるための重要ポイントを解説します。
1. モデルハウスが新築扱いになる条件
- 建築後1年以内であり、登記上の所有者がハウスメーカーになっている場合
- これまで居住者がいなかった場合
2. モデルハウスが中古住宅扱いになるケース
- 建築後1年以上経過している場合
- 見学者の宿泊体験が行われた履歴がある場合
3. 控除を受けるための手続き
- 住宅ローン契約時に金融機関と相談し、控除対象か確認する
- 確定申告時に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出する
モデルハウスを購入する際は、住宅ローン控除の適用条件を確認し、手続きを確実に行うことが重要です。
- モデルハウスは新築扱いになるかどうかは建築後1年以内かつ未入居で決まる
- 住宅ローン控除を受けるには、新築と中古で適用条件が異なる
- モデルハウスは中古住宅として扱われることが多く、控除期間が短くなるケースがある
- 住宅ローン控除の適用には建物の築年数や耐震基準適合証明書の有無が影響する
- 住宅ローンの返済期間は10年以上でなければ控除を受けられない
- モデルハウスの購入時は、住宅ローンの適用範囲を金融機関に事前確認することが重要
- 展示用に使用されていたモデルハウスは修繕費用がかかる可能性がある
- モデルハウスの購入では、借入限度額や控除率が新築と異なることがある
- 一括無料見積もりを活用することで、複数の住宅ローンプランを比較できる
- 2025年の住宅ローン控除は省エネ基準適合が必須条件となる見込み
- 住宅取得資金贈与の非課税措置は2025年まで延長される予定
- モデルハウス購入時には、税制優遇の対象となるかを契約前に確認することが必要
- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告が必要
- 住宅ローンの融資対象に家具・家電が含まれないため、自己資金の準備が必要
- 住宅ローン控除を活用し、長期的な資金計画を立てることが重要

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、
自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。
そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。
気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼
▼オリジナル間取りプランの例▼
『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓
- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい
- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い
- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい




















