
- 大和ハウスの玄関ドアに採用される電気錠の特徴がわかる
- 電気錠と一般的なシリンダーキーの違いを知れる
- 玄関ドアの電気錠の耐用年数と交換の目安を理解できる
- 電気錠を長持ちさせるためのメンテナンス方法を学べる
- 電気錠のリフォーム費用の目安を知れる
- 電気錠の導入によるメリットとデメリットを比較できる
- 導入後に後悔しないための注意点を把握できる

ローコストで家を建てたいなら、
『タウンライフ家づくり』で気になるハウスメーカーを比較・検討してみませんか?
「見積もり」「間取りプラン」「土地探し」の計画書を無料で提案してくれるので、あなたの予算と希望に合った最適なプランが見つかります。
\ 300万円以上の値引き実績あり! /
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
大和ハウスの玄関ドアに電気錠を導入するメリットと特徴
- 玄関ドアの電気錠と一般的な鍵の違い
- 大和ハウスの玄関ドアに採用される電気錠の種類と特徴
- 電気錠のオートロック機能は本当に便利?
- 電気錠を導入すると防犯性はどれくらい向上する?
- 停電時や電池切れの際の対処方法
玄関ドアの電気錠と一般的な鍵の違い

玄関ドアの鍵には、一般的なシリンダーキーと、電気を利用して施錠・解錠を行う電気錠の2種類があります。
シリンダーキーは、物理的な鍵を差し込んで回すことで、ドアの施錠や解錠を行います。
この方式は長年にわたり広く使用されており、シンプルな構造で信頼性が高いという特徴があります。
一方、電気錠は電気の力を利用して鍵の開閉を行うため、物理的な鍵を必要としません。
代わりに、リモコンキー、ICカード、暗証番号、指紋認証、スマートフォンアプリなどのさまざまな手段で施錠・解錠が可能です。
この違いによって、電気錠には多くの利便性が生まれます。
例えば、鍵を持ち歩く必要がなく、ポケットやバッグに入れたままで解錠できるため、荷物が多いときや子供を抱えているときにもスムーズに玄関を通ることができます。
また、オートロック機能が付いている場合、鍵をかけ忘れる心配がなくなり、防犯性が向上します。
しかし、電気錠にはデメリットも存在します。
電気で動作するため、停電時には機能しない可能性があり、非常用の物理キーを持っていないと玄関から入れなくなるリスクがあります。
また、電池式の電気錠では、定期的な電池交換が必要になり、電池が切れてしまうと解錠できなくなることもあります。
さらに、システムが故障した場合、修理や交換が必要になることがあり、シリンダーキーと比べてメンテナンスの負担が増える点も考慮する必要があります。
防犯性の面では、シリンダーキーはピッキングによる不正解錠のリスクがありますが、高性能なディンプルキーを使用すればこのリスクを軽減できます。
一方、電気錠はピッキングの心配がないものの、ハッキングや電子機器の不具合によるトラブルが発生する可能性があります。
そのため、導入する際にはセキュリティ対策がしっかりした製品を選ぶことが重要です。
このように、シリンダーキーと電気錠にはそれぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。
ライフスタイルや防犯意識、使用環境に合わせて最適な鍵を選択することが大切です。
大和ハウスの玄関ドアに採用される電気錠の種類と特徴
大和ハウスの玄関ドアには、さまざまな種類の電気錠が採用されています。
これらの電気錠は、従来の物理的な鍵を使わずに施錠・解錠ができるため、利便性が高く、防犯性にも優れています。
大和ハウスで採用されている主な電気錠の種類を紹介します。
1. リモコンキータイプ
リモコンキータイプは、ポケットやバッグの中にリモコンを入れておけば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠・解錠ができるタイプの電気錠です。
車のスマートキーと同じような感覚で使えるため、非常に便利です。
また、少し離れた場所からリモコン操作で鍵を開けることも可能なので、手がふさがっているときにもスムーズに出入りできます。
ただし、リモコンを紛失すると第三者に悪用されるリスクがあるため、管理には注意が必要です。
2. ICカード・タグキータイプ
このタイプは、専用のICカードやタグキーをドアハンドルにかざすことで施錠・解錠ができるものです。
鍵をポケットやバッグに入れておけば、すぐに出せるため利便性が高いです。
また、ICカードやタグキーは、複数人で共有する場合にも便利です。
ただし、ICカードの磁気が弱くなったり、タグキーを紛失すると使えなくなるため、スペアを用意しておくと安心です。
3. 暗証番号タイプ
暗証番号を入力することで施錠・解錠できるタイプの電気錠も採用されています。
このタイプは、物理的な鍵を持ち歩く必要がないため、鍵の紛失リスクがありません。
また、複数の番号を登録できるモデルもあり、家族全員が自由に使えます。
しかし、番号を他人に見られると防犯上のリスクが高まるため、定期的に番号を変更することが推奨されます。
4. 指紋認証タイプ
指紋を登録することで解錠できる電気錠も、大和ハウスの玄関ドアに採用されています。
このタイプは、鍵やカードを持ち歩く必要がなく、登録された指紋以外では解錠できないため、高い防犯性を誇ります。
ただし、手が汚れていたり、乾燥していたりすると、指紋を正しく認識しないことがあるため注意が必要です。
5. スマートフォンアプリ連携タイプ
スマートフォンのアプリを利用して施錠・解錠できるタイプの電気錠もあります。
このタイプは、外出先からでも鍵の開閉状況を確認できるため、鍵のかけ忘れを防ぐことができます。
また、家族や来客に一時的なアクセス権を与えることも可能です。
ただし、スマートフォンの電池が切れると解錠できなくなる可能性があるため、バックアップとして別の解錠手段を用意しておくと安心です。
このように、大和ハウスの玄関ドアに採用されている電気錠には、さまざまな種類があります。
それぞれの特徴を理解し、ライフスタイルに合った電気錠を選ぶことが重要です。
【関連】大和ハウス公式
電気錠のオートロック機能は本当に便利?

電気錠の大きな特徴の一つが、オートロック機能です。
オートロック機能は、ドアが閉まると自動的に施錠される仕組みであり、鍵のかけ忘れを防ぐことができます。
しかし、利便性が高い一方で、いくつかの注意点もあります。
1. 鍵のかけ忘れを防げる
オートロック機能の最大のメリットは、鍵のかけ忘れを防げることです。
忙しい朝や、子どもを抱えて出かける際などに、鍵を閉めたかどうか気にする必要がなくなります。
また、防犯対策としても有効であり、外出時に自動で鍵がかかることで、不審者の侵入リスクを軽減できます。
2. 閉め出しのリスクがある
オートロック機能には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
最大のデメリットは、鍵を持たずに外出すると閉め出される可能性があることです。
例えば、ゴミ出しなどのちょっとした外出時に鍵を持たずに出てしまうと、家に入れなくなってしまいます。
このため、ICカードやスマートフォンのアプリを活用してバックアップの解錠方法を用意しておくと安心です。
3. 緊急時の対応が必要
オートロック機能を使用する際は、緊急時の対応策を考えておくことが重要です。
例えば、停電時には電気錠が動作しなくなる可能性があるため、物理的なシリンダーキーを常備しておくことが推奨されます。
また、スマートフォンのバッテリー切れや、ICカードの紛失に備えて、予備の鍵を家族や信頼できる人に預けておくと良いでしょう。
4. 自動施錠のタイミングを調整できるモデルもある
一部の電気錠では、オートロック機能の施錠タイミングを調整できるモデルもあります。
例えば、「ドアが閉まってから10秒後に施錠する」といった設定が可能なタイプもあります。
このような機能を活用すれば、閉め出しのリスクを軽減しつつ、利便性を向上させることができます。
オートロック機能は、正しく使用すれば非常に便利な機能ですが、使い方を誤るとトラブルにつながることもあります。
このため、オートロックを利用する際には、緊急時の対応策を考えておくことが重要です。
また、機能のオン・オフを切り替えられるモデルを選ぶことで、状況に応じた使い分けができるため、より快適に使用できます。
電気錠を導入すると防犯性はどれくらい向上する?

電気錠を導入することで、防犯性は大幅に向上します。
一般的なシリンダーキーの場合、ピッキングや鍵の複製による不正解錠のリスクがあります。
一方、電気錠は鍵穴を必要としないモデルも多く、ピッキングによる侵入を防ぐことができます。
また、オートロック機能を搭載した電気錠であれば、鍵のかけ忘れを防止できるため、無施錠による侵入のリスクも軽減されます。
さらに、スマートフォンやICカード、暗証番号、指紋認証といった多様な解錠方法を採用することで、従来の鍵よりもセキュリティレベルを高めることが可能です。
例えば、指紋認証式の電気錠では、事前に登録された指紋のみで解錠が可能となるため、第三者が不正に侵入することは困難です。
また、遠隔操作が可能な電気錠であれば、スマートフォンのアプリを使って施錠状態を確認できるため、外出先からも防犯対策を講じることができます。
万が一、不審な操作や不正な解錠が試みられた場合、警報が鳴る機能が搭載された電気錠もあり、セキュリティ面でのメリットは非常に大きいです。
ただし、電気錠も万能ではなく、システムの故障や電池切れ、ハッキングのリスクも考慮する必要があります。
そのため、物理キーのバックアップや、定期的なメンテナンス、セキュリティソフトウェアのアップデートなどの対策を併せて行うことが重要です。
このように、電気錠は従来の鍵と比較して防犯性を向上させる要素が多いですが、適切な管理と対策が必要となります。
住宅の立地や周辺環境を考慮しながら、自分に最適な電気錠の種類を選ぶことが大切です。
停電時や電池切れの際の対処方法
電気錠は便利な一方で、停電時や電池切れの際に使用できなくなるリスクがあります。
このようなトラブルに備えて、事前に対処方法を把握しておくことが重要です。
まず、電気錠には「電池式」と「電源直結式」の2種類があります。
電池式の場合、定期的な電池交換が必要になりますが、電源が不要なため停電時にも動作するというメリットがあります。
一方、電源直結式の電気錠は、家庭の電力供給に依存するため、停電時には機能しなくなる可能性があります。
そのため、非常用のバッテリーを搭載したモデルを選ぶことで、停電時にも使用できるようになります。
電池式の電気錠の場合、電池残量が少なくなると警告音やLEDランプが点灯して知らせる機能が搭載されていることが多いです。
そのため、警告が出たらすぐに電池を交換することが大切です。
また、万が一電池が完全に切れてしまった場合、外部電源を接続することで一時的に電源供給が可能なモデルもあります。
一部の電気錠では、USBケーブルやモバイルバッテリーを接続することで解錠できる機能が備わっているため、緊急時の対応策として確認しておくと良いでしょう。
また、電源直結式の電気錠を使用している場合、家庭用の非常用電源やUPS(無停電電源装置)を設置することで、停電時にも一定時間電力を供給し、鍵が使えなくなるリスクを軽減できます。
さらに、多くの電気錠には「物理キー(シリンダーキー)」が非常用として付属しています。
これは、電気錠が動作しなくなった際のバックアップ手段として使用できるため、万が一に備えて必ず所持しておくことをおすすめします。
停電や電池切れにより解錠できないトラブルを防ぐためには、日頃からメンテナンスを行い、電池の残量確認や非常用キーの保管場所を定めておくことが大切です。
また、スマートフォンアプリと連携するタイプの電気錠を使用している場合、アプリのアップデートを定期的に行い、システムが最新の状態に保たれているかを確認することも重要です。
このように、電気錠を安全に使用するためには、停電時や電池切れに備えた適切な対策を講じることが不可欠です。
\300万円以上の値引き実績あり!/
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
大和ハウスの玄関ドアに電気錠を導入する際の注意点とコスト
- 玄関ドアの電気錠の耐用年数と交換の目安
- 電気錠を長持ちさせるためのメンテナンス方法
- 電気錠を導入して後悔したケースとは?
- 玄関ドアの電気錠にかかるリフォーム費用の目安
- 電気錠と電子錠の違い、それぞれのメリット・デメリット
- 他社製品と比較!大和ハウスの玄関ドア電気錠の総合評価
玄関ドアの電気錠の耐用年数と交換の目安

電気錠の耐用年数は一般的に7年程度とされています。
これは、電気錠がシリンダーキーとは異なり、電子部品や電動モーターなどの精密機械を含んでいるため、経年劣化の影響を受けやすいからです。
特に、通電による発熱や金属部品の摩耗、電子基板の劣化などが発生するため、長期間使用すると故障や動作不良のリスクが高まります。
また、使用頻度や設置環境によっても耐用年数は変わります。
例えば、1日に何十回も施錠・解錠を行う家庭では、内部の部品が摩耗しやすく、交換が必要になる時期が早まる可能性があります。
また、湿気の多い環境や直射日光が当たる場所に設置されている場合も、電子部品の劣化が早まる要因となります。
交換の目安としては、以下のような症状が現れた場合に検討すると良いでしょう。
- 電気錠の動作が遅くなったり、反応が鈍くなったりする
- リモコンやICカードで解錠ができなくなることが増えた
- オートロック機能が正常に作動しない
- 鍵の開閉時に異音がする
これらの症状が見られる場合は、早めに点検を行い、必要に応じて電気錠の交換を検討することが推奨されます。
また、メーカーによっては定期点検サービスを提供している場合もあるため、長く安全に使用するために、定期的なメンテナンスを行うことも重要です。
電気錠を長持ちさせるためのメンテナンス方法
電気錠を長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
まず、電池式の電気錠を使用している場合は、定期的に電池の残量を確認し、交換のタイミングを逃さないようにすることが重要です。
多くの電気錠は、電池が少なくなると警告音やLEDランプの点灯で知らせてくれますが、突然電池が切れて施錠・解錠ができなくなる可能性もあるため、早めの交換を心がけましょう。
次に、電気錠の動作部分にほこりやゴミが溜まらないように、定期的に掃除をすることも大切です。
特に、指紋認証やタッチパネル式の電気錠では、センサー部分が汚れると正常に認識しづらくなるため、乾いた布で定期的に拭き取るようにしましょう。
また、雨や湿気が原因で電子部品が劣化しないよう、防水対策も施すことが推奨されます。
屋外に設置されている電気錠の場合、防水カバーを使用することで故障のリスクを軽減できます。
さらに、機械式の部品にはシリンダー部分や内部の可動部分に専用の潤滑剤を使用することで、スムーズな動作を維持できます。
ただし、シリンダー部分には一般的な潤滑油を使用しないよう注意が必要です。
油分が内部に詰まり、故障の原因となることがあります。
メーカー推奨の潤滑剤を使用し、適切な頻度でメンテナンスを行いましょう。
定期的なメンテナンスを行うことで、電気錠の寿命を延ばし、安心して使用し続けることができます。
電気錠を導入して後悔したケースとは?

電気錠は非常に便利な設備ですが、導入後に後悔するケースも少なくありません。
特に、オートロック機能による締め出しや、停電時のトラブルが原因で不便さを感じるケースが多く報告されています。
例えば、オートロック機能が有効になっている場合、鍵を持たずに外に出てしまうと、戻れなくなる可能性があります。
特に、ゴミ出しや近所への短時間の外出時に、うっかり鍵を持たずに出てしまい、閉め出されるケースはよくあるトラブルのひとつです。
また、電池切れや停電により、電気錠が作動しなくなるケースもあります。
この場合、物理キーを持っていないと家に入れなくなり、業者を呼んで対応してもらう必要が出てきます。
さらに、スマートフォンアプリと連携するタイプの電気錠では、アプリの不具合やスマートフォンのバッテリー切れにより解錠できなくなることもあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、バックアップとして物理キーを常備することが重要です。
また、オートロック機能の設定を調整し、手動施錠が可能なモードに変更することで、締め出しリスクを低減できます。
電気錠の導入を検討している場合は、これらのリスクを理解し、適切な対策を講じた上で導入することが大切です。
玄関ドアの電気錠にかかるリフォーム費用の目安

玄関ドアに電気錠を導入する際のリフォーム費用は、選ぶシステムの種類や工事の内容によって大きく変わります。
一般的に、電気錠の導入には「既存のドアに後付けする場合」と「玄関ドアごと交換する場合」の2つのパターンがあります。
それぞれのケースについて、費用の目安を詳しく解説します。
まず、既存のドアに電気錠を後付けする場合の費用は、おおよそ 30,000円~100,000円 ほどが目安です。
この価格には、本体価格のほかに、取り付け工事費用が含まれます。
後付け型の電気錠には、ICカード式、リモコンキー式、暗証番号式などの種類があり、製品のグレードによって価格が変動します。
また、電気配線工事が必要な場合は、追加で 10,000円~50,000円 程度の費用がかかることもあります。
一方、玄関ドアごと交換して電気錠を導入する場合は、費用が大きく変わります。
一般的な玄関ドアの交換費用は 200,000円~500,000円 ほどですが、電気錠を組み込んだドアにすることで、さらに 50,000円~150,000円 の追加費用が発生するケースが多いです。
特に、大和ハウスの電気錠付き玄関ドアのように、高機能なモデルを選ぶ場合は、総額で 300,000円~700,000円 になることもあります。
さらに、電気錠には「電池式」と「電源直結式」があります。
電池式は電気配線工事が不要なため、初期費用を抑えることができますが、定期的な電池交換が必要です。
一方、電源直結式は停電時の対応が必要になるものの、電池交換の手間が不要で、長期的なランニングコストを抑えられるというメリットがあります。
また、リフォーム費用には、補助金を活用できる場合があります。
例えば、国や自治体が提供する省エネ住宅改修補助金や防犯対策補助金を利用することで、電気錠導入費用の一部を軽減できることがあります。
リフォームを検討する際は、補助金の対象となるかどうかを事前に確認し、賢くコストを抑える工夫をするのがおすすめです。
このように、電気錠のリフォーム費用は、選ぶタイプや施工方法によって大きく変動します。
自宅の玄関の構造やライフスタイルに合った電気錠を選ぶことで、無駄な費用を抑えつつ、安全性と利便性を向上させることが可能です。
電気錠と電子錠の違い|それぞれのメリット・デメリット
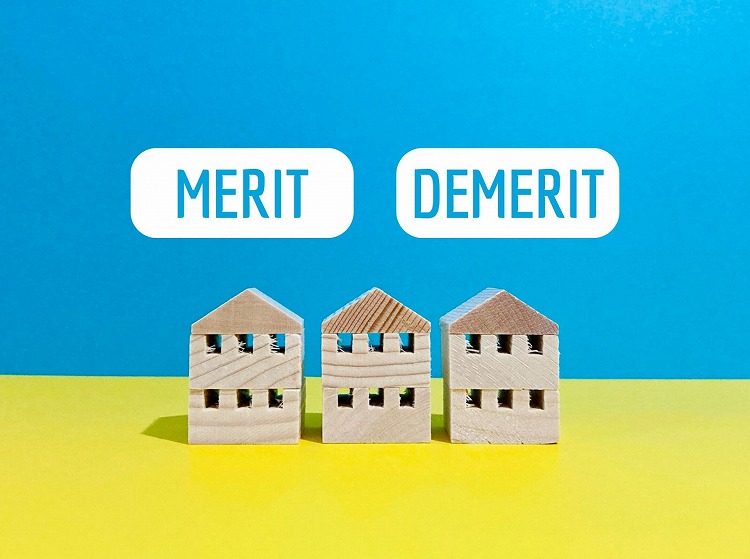
電気錠と電子錠は、どちらも従来の物理的な鍵を使わずに施錠・解錠を行うシステムですが、それぞれ異なる特徴があります。
両者の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
まず、電気錠は、電源からの供給を受けて動作する鍵のことを指します。
このタイプの鍵は、オートロック機能を搭載しているものが多く、建物の出入りを一括管理できる点が特徴です。
主に、オフィスビルやマンションのエントランス、セキュリティの厳しい施設などで採用されることが多いですが、近年では一般住宅にも導入が進んでいます。
一方、電子錠は、電池を使用して動作するものが一般的で、シリンダーキーの代わりに暗証番号、ICカード、スマートフォン、指紋認証などで解錠するシステムを指します。
電気配線工事が不要なため、既存のドアに後付けしやすいというメリットがあります。
それぞれのメリット・デメリットを以下にまとめます。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 電気錠 | オートロック機能が利用できる / 遠隔操作で解錠が可能 / セキュリティ管理がしやすい | 停電時には作動しない場合がある / 電気配線工事が必要 / 初期費用が高い |
| 電子錠 | 電気工事が不要 / 比較的安価に導入できる / さまざまな解錠方法を選べる | 電池交換が必要 / オートロック機能がないものもある / セキュリティ機能が製品によって異なる |
このように、電気錠と電子錠にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
一般的な住宅で利便性を重視するなら「電子錠」、より高度な防犯対策を求めるなら「電気錠」が適しています。
どちらを選ぶかは、自宅の防犯レベルや生活スタイルに合わせて検討することが重要です。
他社製品と比較!大和ハウスの玄関ドア電気錠の総合評価

大和ハウスの玄関ドアに採用されている電気錠は、他社製品と比較しても優れた機能を備えています。
特に、防犯性と操作性のバランスが取れており、多くの住宅で導入が進んでいます。
他社の電気錠と比較しながら、大和ハウスの電気錠の特徴を評価します。
まず、大和ハウスの電気錠は、リモコンキー、ICカード、スマートフォンアプリ、暗証番号、指紋認証など、複数の解錠方法に対応している点が特徴です。
これにより、利用者の好みに応じた施錠・解錠が可能となり、鍵を持ち歩かなくても良い利便性があります。
一方、他社の電気錠は、ICカードや暗証番号のみに対応しているものが多く、スマートフォン連携機能を搭載している製品は限られています。
また、大和ハウスの電気錠は、オートロック機能を標準装備しており、鍵のかけ忘れを防げる仕様になっています。
他社製品の場合、オートロック機能がオプションで追加費用が発生するケースもあるため、コストパフォーマンスの面でも大和ハウスの電気錠は優れています。
さらに、大和ハウスの玄関ドア電気錠は、耐久性が高く、定期的なメンテナンスがしやすいという点も評価できます。
専用の防水・防塵設計が施されているため、屋外環境でも長期間にわたって安定した動作を維持できます。
他社製品では、屋外設置に対応していないモデルもあり、環境によっては故障しやすくなることもあるため、耐久性の面でも大和ハウスの電気錠は優れた選択肢と言えます。
このように、大和ハウスの玄関ドア電気錠は、他社製品と比較しても高い利便性と防犯性を備えており、長期的な視点で見ても安心して使用できる優れた製品です。
- 玄関ドアの鍵にはシリンダーキーと電気錠の2種類がある
- 電気錠は物理的な鍵を使わずに施錠・解錠ができる
- 電気錠はリモコンキー、ICカード、暗証番号、指紋認証などで操作可能
- 大和ハウスの玄関ドアには複数の電気錠の種類がある
- オートロック機能があり、鍵のかけ忘れを防げる
- 電気錠はピッキング被害を防止し、防犯性を向上させる
- 電池切れや停電時の対策として物理キーを持つことが推奨される
- 定期的なメンテナンスを行うことで電気錠の寿命を延ばせる
- 電気錠の耐用年数は一般的に7年程度とされている
- リモコンキーやICカードは紛失時のリスクがあるため管理が重要
- スマートフォンアプリと連携し、遠隔で施錠・解錠が可能なモデルもある
- 電気錠のリフォーム費用は種類や施工方法によって異なる
- 他社製品と比較して、大和ハウスの電気錠は防犯性と操作性のバランスが良い
- 電気錠の導入を検討する際は、停電やシステム障害への備えが必要
- 住宅環境やライフスタイルに合わせた電気錠の選択が重要

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、
自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。
そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。
気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼
▼オリジナル間取りプランの例▼
『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓
- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい
- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い
- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい




















