
三井ホームの注文住宅に興味があるけれど、冬の寒さに耐えられるのか心配だと感じている方も多いのではないでしょうか。
実際に住んでみて寒いと感じた人の体験談や、全館空調の特徴と費用、床下暖房の仕組みまで知っておきたいという声も多く寄せられています。
この記事では、三井ホームの断熱性能や寒さに関する評価を中心に、コスパの良い一戸建ての寒さ対策まで詳しくご紹介していきます。
断熱性能が高いハウスメーカーの比較や、実際に導入する際のチェックポイントもわかりやすくまとめていますので、これから家づくりを検討されている方にとって参考になるはずです。
-
三井ホームの住宅が本当に寒いのかどうかが分かる
-
寒さの原因となる設計や仕様のポイントを理解できる
-
全館空調スマートブリーズの特徴と費用が分かる
-
床下暖房の仕組みと導入費用を把握できる
-
一戸建てでできるコスパの良い寒さ対策を知ることができる
-
他ハウスメーカーとの断熱性能の違いを比較できる
-
寒さ対策として未来発電Gの活用方法を学べる
\300万円以上の差がつく/
複数社比較の相見積もりは
やらないと損!!
▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼
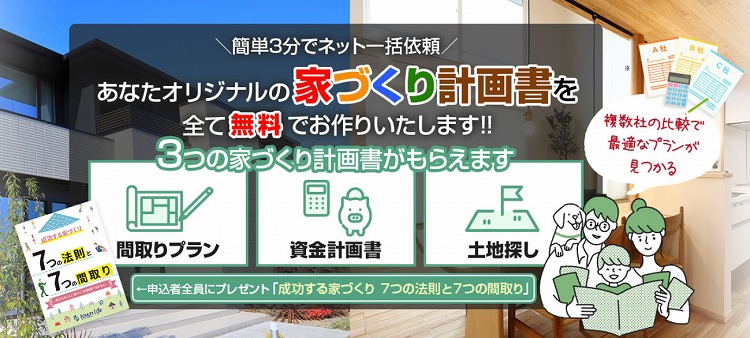 1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です
希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ
さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!
▼成功する家づくりプレゼント▼
- 希望の家の質問に回答(約3分)
- ハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
三井ホームは寒いのか?実際の住み心地と評価
-
三井ホームは寒い?住んでみてのリアルな感想
-
全館空調「スマートブリーズ」とは
-
全館空調の設置費用とランニングコスト
-
三井ホームの床下暖房の特徴と費用を解説
三井ホームは寒い?住んでみてのリアルな感想

三井ホームの注文住宅に住んでみて「寒い」と感じるかどうかは、多くの人にとって関心の高いポイントです。
実際に三井ホームで建てた家に住んでいる施主の体験談を集めてみると、その印象は二分される傾向があります。
まず、三井ホームの住宅は基本的に断熱性能の高い構造で建てられており、全館空調「スマートブリーズ」との相性もよいため、「家中が快適に保たれている」「外が寒くても家の中は一定の温度で過ごしやすい」という声が多く聞かれます。
とくに寒さが厳しい冬の時期でも、玄関やトイレ、廊下など家の中で寒さを感じにくいというメリットがあります。
一方で、「寒い」と感じる意見も一部には存在します。
その理由としては、以下のようなケースが考えられます。
・吹き抜けや大空間を多く取り入れた間取りにしてしまい、暖気が上に溜まりやすくなった
・断熱仕様を最低ランクで建ててしまった
・気密性の確保が不十分だった
・床材が冷たく、足元の冷えを感じやすい構造になっていた
このような事例を見ると、「三井ホームだから寒い」というよりも、「設計段階で断熱仕様や空調計画をどのように選択したか」によって、快適性に差が出ていることがわかります。
また、建築地域の気候条件や施主の寒さへの感受性によっても体感は異なります。
さらに、全館空調を使わずに通常のエアコンのみで運用している場合は、温度のムラが発生しやすくなり、部屋によっては寒さを感じる場面もあるかもしれません。
したがって、三井ホームに住んで寒いかどうかは、「三井ホームでどんな仕様にしたか」に大きく左右されるというのが実情です。
断熱等級6~7への対応、全館空調の導入、床材の選び方などを工夫することで、冬でも暖かく快適な住空間を実現できるでしょう。
【関連】三井ホーム公式
全館空調「スマートブリーズ」の特徴やバリエーション
三井ホームの全館空調「スマートブリーズ」は、快適な住環境を実現するために開発された独自の空調システムです。
このシステムは、一般的なエアコンと異なり、1台の空調機器で家全体の空気を循環させることで、温度と湿度を一定に保ちます。
そのため、部屋ごとの温度差がなく、玄関・廊下・洗面所・トイレなどの居室以外の場所でも快適に過ごすことができます。
スマートブリーズの大きな特徴は、加湿・除湿・換気・空気清浄などを1台でこなす多機能性です。
とくに「加湿機能」が標準搭載されている点は、冬の乾燥対策に非常に有効です。
この機能により、冬場でも肌や喉の乾燥を感じにくく、コンタクトレンズ利用者などにも優しい環境を提供してくれます。
また、吹き出し口が各部屋に小さく分散されているため、風が直接当たりにくく、冷暖房による不快感も軽減されます。
スマートブリーズには主に3つのバリエーションがあります。
・スマートブリーズ・エース(加湿機能・部屋別温度調整付き、設置場所が選べる)
・スマートブリーズ・プラス(加湿機能・部屋別風量調節付き、床置きタイプ)
・スマートブリーズ・ワン(加湿なし、40坪以下の住宅向け、コスト重視)
スマートブリーズ・エースとプラスは高性能な反面、初期費用とランニングコスト(毎年25,000円のメンテナンス契約など)が発生します。
また、万が一故障した場合は100万円前後の修理費用がかかることもあります。
一方、スマートブリーズ・ワンは加湿機能はないものの、エアコン1台で運用できるため、導入費用が抑えられ、故障時の交換コストも少ないというメリットがあります。
このように、ライフスタイルや予算に応じて選べるのがスマートブリーズの強みです。
また、三井ホームの構造は、ダクトを通すための床や天井のスペース設計にも配慮されており、スマートブリーズとの相性が非常に良いとされています。
室内のどこにいても温度差が少なく、快適で健康的な暮らしを実現したい人には、非常におすすめできる設備です。
全館空調の設置費用とランニングコスト

三井ホームの全館空調「スマートブリーズ」は、快適性と省エネ性を両立した人気の高い設備ですが、気になるのはその設置費用とランニングコストです。
まず設置費用についてですが、スマートブリーズには主に3つのバリエーションがあります。
高性能な加湿機能付きモデルである「スマートブリーズ・プラス」「スマートブリーズ・エース」、そして加湿機能のないコンパクトな「スマートブリーズ・ワン」です。
プラスとエースについては、導入コストとしておおよそ200万円〜300万円程度が相場となります。
これはエアコン1台だけで運用する方式と比べると高額ではありますが、全館空調は家全体を快適に保つための価値ある投資といえるでしょう。
一方で「スマートブリーズ・ワン」は、導入費用を大幅に抑えられ、100万円〜150万円ほどで済むことが多いです。
ただし加湿機能や個別調整機能がない点には注意が必要です。
ランニングコストについては、機種や建物の広さ、住んでいる地域の電気料金にも左右されますが、目安として月に8,000円〜12,000円程度となります。
また、スマートブリーズ・プラスとエースは、3年目以降に年間25,000円前後のメンテナンス契約費用が発生します。
この点は見落とされがちなので注意が必要です。
さらに、故障や部品交換が発生した際の修理費用が高額になることもあります。
全館空調は高性能ゆえに、万が一の故障時には100万円前後の修理費が必要となるケースもあるため、長期的なメンテナンス計画をしっかり立てることが重要です。
一方で、電気代の高騰が続く今、三井ホームが提案している「未来発電G」という太陽光パネル+エネファームのセット提案を活用することで、ランニングコストを抑えることも可能です。
この制度では、太陽光パネルの初期費用が無料となる代わりに、10年間の売電収入が東京ガス側に渡る仕組みです。
その分、電気を買う量が減るため、全館空調の電気代も節約につながります。
このように、三井ホームの全館空調は初期費用が高めではありますが、快適さや健康、長期的な省エネ効果を考えれば、十分に導入価値がある設備といえます。
導入を検討する際には、各モデルの機能性とメンテナンス費用を比較し、自身のライフスタイルや家族構成に合った機種を選ぶことがポイントです。
三井ホームの床下暖房の特徴と費用を解説

三井ホームの寒さ対策の一つに「床下暖房」の導入があります。
この設備は、床の下に設置された温水配管や電熱ヒーターによって、足元からじんわりと室内を暖めるシステムです。
三井ホームでは基本的に全館空調が主力の暖房設備となっていますが、冷え込みが厳しい地域や、冷え性に悩む方のために、床下暖房を部分的に併用するケースもあります。
床暖房と違い、床そのものが熱くなるわけではなく、床下空間から輻射熱と対流熱で室温をじんわりと上げていく仕組みになっているため、自然な温かさを感じやすいのが特徴です。
また、床材を選ばず施工できることや、床が熱くなりすぎないので小さなお子様や高齢者にも安心という利点もあります。
導入される場所としては、脱衣所や洗面所、キッチン、リビングの一部などが多く、冷え込みやすい場所の足元対策として有効です。
設置費用については、床面積10㎡あたりで20万円〜30万円前後が一般的な相場となっています。
リビング全体に導入する場合は50万円〜100万円程度かかることもあるため、予算とのバランスを見て導入範囲を検討することが重要です。
また、運転方式には「電気式」と「温水式」の2種類があり、三井ホームでは多くの場合、温水式床下暖房が選ばれます。
この方式は一度の設置コストは高めですが、ランニングコストが低く、長期的に見れば経済的です。
一方で、電気式は設置が簡単な反面、運転コストがやや高くなる傾向があるため、短時間だけの運用を想定している人向きです。
なお、床下暖房は家具の下に設置する必要がないため、レイアウトの自由度が高い点も魅力です。
さらに、室内の空気を乾燥させにくく、ホコリが舞いにくいという健康面のメリットも見逃せません。
一方で、全館空調と比べると温まり方に時間がかかることがあるため、タイマー運転やサブ暖房との併用などで対策するのが一般的です。
結論として、三井ホームの床下暖房は冷え対策として非常に効果的で、特に部分的な採用でも快適性を高めることができます。
寒冷地や脱衣所の温度差が気になる方には、全館空調との併用をおすすめします。
\300万円以上の値引き実績あり!/
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
三井ホームで寒さ対策をするためのポイントとは?
-
一戸建ての寒さ対策で効果的な方法とは?
-
コスパの良い寒さ対策グッズ4選【手軽にできる】
-
ハウスメーカーの断熱性能ランキングに見る選び方
-
三井ホームの断熱性能はどれくらい高い?
-
三井ホームの寒さ対策に「未来発電G」は有効?
-
三井ホームは寒い?後悔しないためのチェックポイント
一戸建ての寒さ対策で効果的な方法とは?

一戸建て住宅に住んでいると、冬の寒さがじわじわと室内に影響してくるのを感じる場面が少なくありません。
特に、マンションに比べて気密性が低く、窓や床、天井からの冷気の侵入に悩まされることが多いのが一戸建ての特徴です。
そこで効果的な寒さ対策として、まず押さえておきたいのが「断熱」「気密」「空調管理」の3つの視点です。
断熱の基本は、熱を逃がさない・入れないという発想にあります。
断熱性能が高い家は、冬でも室温が安定しやすくなり、暖房効率も向上します。
一方、気密性が低いと、いくら断熱材を強化してもすき間から冷気が入り込み、室内の温度は保ちにくくなります。
そのため、サッシの隙間や配管まわりなど、小さなすき間の補修も重要な寒さ対策の一つです。
次に空調管理ですが、ここで注目したいのは床下や壁内、天井内に温風や温水を巡らせる「全館空調」や「床暖房」「床下暖房」の導入です。
特に全館空調は、家全体を24時間一定の温度に保つことができ、寒暖差のストレスがなくなります。
また、リビング階段や吹き抜けといった寒くなりがちな空間でも快適に保てるのが魅力です。
高齢の家族がいる場合は、急激な温度差によるヒートショックの予防にもつながります。
さらに、窓の対策も大きなポイントです。
複層ガラス(ペアガラス)やトリプルガラス、樹脂サッシへの変更は、断熱性能を劇的に改善します。
これが難しい場合は、内窓の設置や断熱フィルムの貼り付けなども有効です。
予算に余裕があれば、外壁や屋根の断熱リフォームを検討するのもよいでしょう。
ただしこれらは費用がかさむため、補助金や税制優遇を活用するのが賢い選択です。
コスパの良い寒さ対策グッズ4選【手軽にできる】
断熱性能でおすすめのハウスメーカー一覧(UA値付き)

住宅の断熱性能を重視してハウスメーカーを選ぶ際には、「UA値(外皮平均熱貫流率)」という数値を見ることが大切です。
UA値は、家全体の屋根・壁・床・窓などを通じて外へ逃げてしまう熱の平均値を示すもので、この数値が小さいほど高断熱であることを表しています。
2025年には、住宅の断熱基準として「断熱等性能等級5」が事実上の義務化になりますが、実際に断熱性能で先行しているハウスメーカーは、そのさらに上の等級6や等級7にすでに対応済みです。
ここでは、実際の断熱性能(UA値)を基準に、断熱性能が特に優れているとされるハウスメーカーを紹介します。
視覚的にわかりやすく、箇条書きでそれぞれのハウスメーカーの特徴とともにご説明していきます。
-
一条工務店(UA値:0.25〜0.28W/㎡・K)
業界でも断熱性能に特化した代表格のメーカーです。
標準仕様で「トリプル樹脂サッシ」「高性能ウレタン断熱材」「基礎断熱」などを組み合わせており、断熱等級7にも標準で対応しています。
外皮平均熱貫流率であるUA値は、国内トップレベルの0.25前後を誇り、寒冷地でも快適に暮らせる家を提供しています。
また、高気密施工(C値0.59以下)も標準対応しているため、断熱材の性能をしっかりと発揮できる施工精度も大きな強みです。
-
ダイワハウス(ウルトラW断熱仕様・UA値:0.27W/㎡・K前後)
木造住宅「xevoGranWood」における最上位仕様「ウルトラW断熱」が非常に高性能です。
壁・床・天井それぞれに高密度な断熱材を分厚く施し、かつトリプルガラスや外張り断熱まで組み合わせているのが特徴です。
ダイワハウスはもともと鉄骨住宅のイメージが強いですが、この木造ラインの断熱仕様は非常に優れており、断熱性能で選ぶなら検討価値が高いモデルです。
-
三井ホーム(MOCX THERMO仕様・UA値:0.39W/㎡・K)
三井ホームは木造2×6構造に独自の「プレミアム・モノコック構法」を組み合わせた、高断熱高気密な家づくりが特徴です。
「MOCX THERMO(モクスサーモ)」仕様では、壁140mm+外張り100mmのダブル断熱構成となっており、等級7にも対応可能です。
また、トリプルガラス・樹脂サッシ・高断熱玄関ドア・屋根断熱パネル(DSP)など、外皮全体の断熱対策も一通り揃っています。
加えて、全館空調「スマートブリーズ」との併用により、空調効率を最大限に高めることで、快適性と省エネを両立しています。
-
住友林業(BF構法・UA値:0.41〜0.46W/㎡・K)
住友林業では、木造でありながら鉄骨のような構造設計ができる「ビッグフレーム構法(BF構法)」が特徴です。
この構法により間取りの自由度を高めつつ、UA値0.41〜0.46程度の断熱性能も確保しています。
寒冷地仕様にすれば等級6にも対応可能ですが、標準では等級5〜6の中間あたりと見られるため、希望があれば強化を要望するのが良いでしょう。
また、気密性の確保についてはオプション扱いになることが多いので、注意が必要です。
-
パナソニックホームズ(HS構法・UA値:0.46〜0.50W/㎡・K)
鉄骨住宅でありながら断熱性能にも配慮しているメーカーです。
外張り断熱と内断熱を併用し、さらに全館空調システムと一体化させることで、快適な温熱環境を実現しています。
他社に比べるとUA値は若干劣るものの、メンテナンス性や工業化による施工精度の高さから、都市部での家づくりに向いています。
また、東京ゼロエミ住宅の基準に最も対応しやすいハウスメーカーとしても評価されています。
-
積水ハウス(シャーウッド構法・UA値:0.40〜0.46W/㎡・K)
積水ハウスの木造商品「シャーウッド」シリーズは、外張り断熱と充填断熱の併用で断熱性能を強化しています。
ZEH仕様にすれば等級6相当、さらに寒冷地仕様を選べば等級7にも届く断熱設計が可能です。
ただし、標準仕様では等級5前後に留まる場合があるため、寒さ対策を徹底したい方は強化プランの選択が必要になります。
外観デザインの自由度や構造の強度にも定評があるため、トータルバランスで選ばれることが多いメーカーです。
ここまで、実際の断熱性能(UA値)を基に、断熱に強いハウスメーカーを比較してきました。
UA値が低いほど断熱性能が高く、例えば一条工務店のようにUA値0.25以下であれば、極寒の地域でも快適な室温を保つことが可能です。
しかし、UA値だけを見て判断するのは早計です。
断熱材の種類や施工精度、窓の性能、気密性、全館空調との相性、さらには補助金や維持費の観点まで含めて、総合的に判断することが大切です。
例えば三井ホームでは、単に断熱材が厚いだけでなく、構造体(モノコック構法)や全館空調、さらには「未来発電G」などのランニングコスト対策も用意されており、トータル性能で選ばれる理由があります。
どのハウスメーカーも、オプションによって断熱仕様を強化できる場合がありますが、それには当然コストが伴います。
複数のハウスメーカーから一括でプラン・見積もりを取り寄せることで、自分の予算や希望に最適な提案を受け取ることができます。
その際には「タウンライフ家づくり」のような無料の一括請求サービスを使うと、手間なく比較検討ができておすすめです。
断熱性能は、今後何十年と快適に暮らすための“住宅性能の土台”とも言える重要な要素です。
しっかりと情報を整理して、後悔のない家づくりを進めていきましょう。
三井ホームの断熱性能はどれくらい高い?
三井ホームの断熱性能は、一般的なハウスメーカーと比べても非常に高い水準にあります。
特に注目すべきは、独自の「プレミアム・モノコック構法」による断熱構造です。
この構法では、屋根、壁、床の各面に対して断熱材をしっかりと配置しており、外部の気温変化を最小限に抑えることができます。
屋根には「ダブルシールドパネル(DSP)」という高断熱仕様の構造体を使用しており、夏の日射熱を効果的に遮断します。
壁には2×6材を使った分厚い構造の中に、高性能グラスウール140mmをしっかり充填しています。
また、外側にはフェノールフォーム断熱材を100mm追加した「内外ダブル断熱」に対応することも可能です。
これは、断熱等性能等級7をクリアするための仕様であり、最高レベルの断熱性能といえます。
床部分にはトラスフロア構造を採用し、床下に断熱材をしっかりと組み込みつつ、空気の循環も考慮されています。
さらに窓には、樹脂フレームとトリプルガラスを組み合わせた高性能サッシが採用されています。
このように建物の外皮全体で熱の出入りを抑える構造が整えられており、断熱性能の指標であるUA値では、0.39W/㎡Kという業界トップクラスの数値を実現しています。
これは、国が定めるZEH基準(断熱等級5)をはるかに上回る性能であり、北海道や東北といった寒冷地にも対応できる水準です。
断熱性能は、体感温度の快適さだけでなく、光熱費の節約、健康リスクの低下(ヒートショック対策)にも大きく関係してきます。
そのため、三井ホームの断熱仕様は、長期的に安心して暮らせる住まいを求める方にとって、大きなメリットとなるでしょう。
なお、断熱性能を最大限に活かすためには、現場での施工精度や気密性(C値)にも注意が必要です。
三井ホームでは、希望すれば気密測定オプションを追加できるため、こだわりたい方はぜひ活用しましょう。
三井ホームの寒さ対策に「未来発電G」は有効?

三井ホームの寒さ対策において、「未来発電G」は非常に効果的な選択肢の一つです。
この制度は、東京ガスが提供するエネファーム(家庭用燃料電池)を導入することで、太陽光パネルが無償で提供されるという仕組みです。
光熱費を抑えつつ、全館空調などの電力を多く消費する設備との相性も良いため、寒い冬に備える上で実用的な寒さ対策となります。
寒さ対策における重要なポイントは、単に断熱性能を上げるだけではありません。
冬場は暖房費の増加が家計を圧迫しがちですが、「未来発電G」によって家庭内で自家発電を行うことで、電力会社から購入する電気の量を大幅に減らすことができます。
その結果、暖房の使用頻度が増える冬場でも、経済的な負担を軽減できます。
また、エネファームは発電と同時に発生する熱を利用してお湯を作るため、給湯にもエネルギー効率よく対応できます。
家全体で見ると、発電、暖房、給湯が連携することで、エネルギー消費の最適化が図れるのです。
さらに、「未来発電G」は災害時の停電対策としても注目されています。
万が一の際にもエネファームや太陽光発電からの電力供給が可能であるため、冬場の寒さから家族を守る安心感につながります。
ただし、この制度には注意点もあります。
最初の10年間は太陽光による売電収入は東京ガス側に帰属する仕組みのため、売電による利益を自分で得ることはできません。
それでも、電気代の削減効果や災害対策としての価値を考えると、十分にメリットのある制度といえるでしょう。
初期費用を抑えながら高性能な暖房環境を整えたい方には、「未来発電G」は非常におすすめの制度です。
三井ホームは寒い?後悔しないためのチェックポイント

三井ホームに関して、「実際寒いのでは?」という声が見られることがありますが、これは構造の理解不足や設備選びのミスマッチが原因であることが多いです。
基本的に三井ホームの住宅は、構造体である「プレミアム・モノコック構法」や断熱材の厚み、屋根断熱パネル、全館空調などを組み合わせることで、非常に高い断熱性・気密性を実現しています。
では、なぜ「寒い」と感じてしまう人がいるのでしょうか。
その主な原因は3つあります。
まず1つ目は、全館空調の使い方に問題があるケースです。
三井ホームではスマートブリーズという全館空調システムを導入できますが、稼働時間や温度設定を適切に行わなければ、寒さを感じてしまうことがあります。
タイマー運転や部分停止を過剰に設定してしまうと、家全体の温度が安定せず、寒さが目立ってしまうのです。
2つ目は、気密施工の有無です。
三井ホームでは気密測定オプションがありますが、標準で施工されるわけではありません。
そのため、C値(隙間相当面積)の測定を行っていない場合、すき間から冷気が侵入し、体感温度が下がってしまうことがあります。
これを防ぐには、契約時点で気密施工を追加するように依頼することが重要です。
3つ目は、断熱仕様の選択ミスです。
三井ホームは等級5〜7に対応できる断熱構成を用意していますが、価格や間取り重視で選んだ結果、断熱性能が不十分な仕様になってしまうこともあります。
特に寒冷地では、内外ダブル断熱やトリプルガラスの採用が非常に重要になります。
後悔しないためには、次の3つのチェックポイントを意識しましょう。
・断熱仕様は「等級6以上」かつトリプルガラス+樹脂サッシを採用する
・スマートブリーズ導入時には、メンテナンスや操作性も理解したうえで利用する
・気密施工オプションを忘れずに追加する
また、初期費用を抑えつつ暖房費の負担を減らすためには「未来発電G」などの制度も活用しながら、バランスの良い設備構成にすることが重要です。
住宅購入は大きな投資だからこそ、情報収集を徹底し、性能面での後悔がないようにしましょう。
・断熱性能が高い一方で、仕様選択や施工精度によって寒さを感じる場合もある
・スマートブリーズは加湿・除湿・換気・空気清浄を1台で行える全館空調システムである
・スマートブリーズには3つの種類があり、性能と価格に差がある
・全館空調の導入費用は100万円〜300万円で、ランニングコストも考慮が必要
・床下暖房は輻射熱で自然な暖かさを提供し、部分採用にも向いている
・床下暖房の費用は設置範囲によって異なり、10㎡あたり20万〜30万円が目安
・一戸建てでは断熱・気密・空調の3要素が寒さ対策の基本となる
・断熱カーテンや吸湿発熱ラグなど、安価で効果的な寒さ対策グッズが多く存在する
・三井ホームの断熱等級7仕様は、UA値0.39で業界トップクラスの性能を持つ
・「未来発電G」を使えば、太陽光パネルが実質無料で導入できる
・エネファームとの併用で電気代削減と災害時の備えにもなる
・断熱性に優れたハウスメーカーは他にもあり、一条工務店やダイワハウスが高評価
・三井ホームは高断熱仕様でも、気密測定オプションを付けないと性能を活かせない
・「三井ホーム 寒い」と感じた人の多くは、断熱や空調の選択ミスが原因である

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、
自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。
そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。
気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼
▼オリジナル間取りプランの例▼
『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓
- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい
- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い
- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい






















