
マイホームの外観デザインを考える上で、意外と見落とされがちながら、家の印象や性能に大きな影響を与える部分があります。
それが、屋根の先端部分である「軒(のき)」の裏側、すなわち積水ハウスの軒裏です。
積水ハウスをご検討中の方の中には、この軒裏のデザイン性や機能性、標準仕様とオプションにはどのような違いがあるのか、また費用はどのくらいかかるのか、といった具体的な情報を求めている方も多いのではないでしょうか。
例えば、軒裏に木目調のデザインを取り入れることで、建物全体に高級感や温かみを加えられますし、その機能性に注目すれば、外壁の劣化を予防し、住まいの寿命を延ばすという重要なメリットも理解できます。
しかし、デザインや素材の選択肢が豊富なだけに、どのような基準で選べば良いのか、設計段階で気をつけるべきポイントは何か、そして後から後悔しないためにはどのようなデメリットを把握しておくべきか、悩みは尽きないかもしれません。
この記事では、積水ハウスの軒裏について、その美しいデザインのバリエーションから、住まいを守る優れた機能性、さらには標準仕様とオプションの違い、屋根材との組み合わせ、メンテナンス方法に至るまで、あらゆる角度から徹底的に解説していきます。
これから家づくりを始める方が、満足のいく選択をするための一助となれば幸いです。
なお、ハウスメーカー各社の資料・カタログはコチラから入手すると、無料&まとめて一括請求できるので比較検討がとてもカンタンで便利です。
- 積水ハウスの軒裏が持つ多彩なデザインバリエーション
- 軒裏が家の耐久性に与える重要な機能性
- 標準仕様とオプションで選べる素材やデザインの違い
- 軒裏を選ぶ際に知っておくべきメリットとデメリット
- 屋根材と軒裏を組み合わせる際の設計ポイント
- オプション選択時の費用感とコストを抑えるコツ
- 美観を長持ちさせるためのメンテナンス方法
\300万円以上の差がつく/
複数社比較の相見積もりは
やらないと損!!
▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼
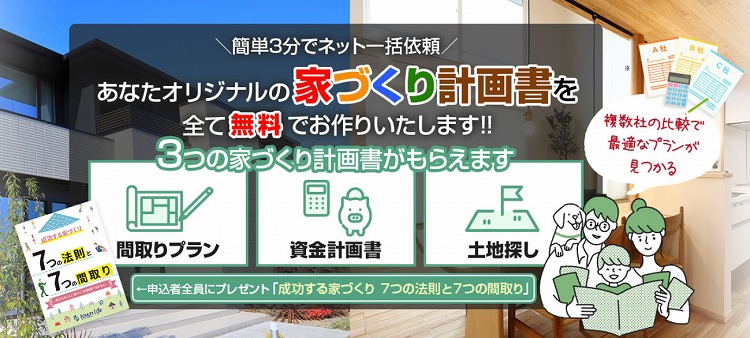 1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です
希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ
さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!
▼成功する家づくりプレゼント▼
- 希望の家の質問に回答(約3分)
- ハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
積水ハウスの軒裏が持つデザインと機能性の魅力
- 軒裏のデザインで外観の印象は大きく変わる
- 木目調など豊富なデザインから選べる軒天
- 標準仕様とオプションで選べる軒裏の素材
- 軒裏が果たす外壁保護などの重要な役割
- 高級感と耐久性を両立する軒裏の機能性
軒裏のデザインで外観の印象は大きく変わる

住宅の外観は、家全体の第一印象を決定づける非常に重要な要素です。
その中でも、積水ハウスの軒裏は、建物の表情に深みと個性を与える上で、想像以上の役割を果たします。
軒裏とは、屋根の先端が外壁から突き出している部分(軒)の裏側のことで、普段はあまり意識しない場所かもしれません。
しかし、この部分のデザインや素材感ひとつで、住まい全体のテイストは大きく変化するのです。
例えば、軒に十分な深さを持たせ、その裏側を丁寧に仕上げることで、建物に重厚感と安定感が生まれます。
軒のラインがくっきりと見えることで、空と建物の境界が美しく縁どられ、彫りの深い、陰影に富んだ外観を演出できるでしょう。
これは、日本の伝統的な建築美にも通じる考え方であり、積水ハウスはこうした細部のデザインを大切にしています。
また、軒裏の色や素材を外壁や窓枠とコーディネートすることで、建物全体に統一感が生まれます。
例えば、濃い色の外壁に明るい木目調の軒裏を合わせれば、温かみのあるアクセントとなり、モダンでありながらもナチュラルな雰囲気を醸し出せます。
逆に、シンプルな白い外壁に同系色のすっきりとした軒裏を組み合わせれば、クリーンで洗練された印象が際立ちます。
積水ハウスでは、多様な建築スタイルに対応できるよう、軒裏のデザインにも豊富なバリエーションを用意しています。
そのため、施主のこだわりや理想のイメージを細部にまで反映させることが可能です。
単に雨風をしのぐという機能だけでなく、軒裏を「第二の天井」として捉え、デザイン要素として積極的に活用することで、ありきたりではない、ワンランク上の外観デザインを実現することができるのです。
家づくりにおいて、外壁や屋根材に注目が集まりがちですが、ぜひこの軒裏のデザインにも目を向けてみてください。
その小さな面積が、あなたの家の個性を雄弁に物語るキーパーツになるかもしれません。
【関連】積水ハウス公式
木目調など豊富なデザインから選べる軒天
積水ハウスの軒裏、専門的には「軒天(のきてん)」とも呼ばれるこの部分は、デザインの選択肢が非常に豊富で、施主のこだわりを表現できるキャンバスのような場所です。
特に人気が高いのが、木の温もりと質感を再現した木目調のデザインです。
本物の木材を使用すると、経年変化による劣化やメンテナンスの手間が気になりますが、積水ハウスが提供する木目調の軒天材は、高い耐久性と耐候性を備えています。
そのため、長期間にわたって美しい表情を保ち続けることができるのです。
木目調デザインの中にも、さまざまなバリエーションが存在します。
例えば、明るくナチュラルな印象を与えるライトな色合いのオーク調、重厚感と高級感を演出するダークなウォールナット調、和モダンな雰囲気にぴったりの落ち着いたチェリー調など、多彩なカラーと木目のパターンから選べます。
これにより、洋風、和風、モダン、ナチュラルといった、あらゆる住宅スタイルに違和感なく調和させることが可能です。
軒裏を木目調にする最大のメリットは、建物に自然素材のような温かみと上質感をプラスできる点にあります。
特に玄関ポーチやウッドデッキの上の軒裏に木目調を採用すると、内と外をつなぐ空間に一体感が生まれ、リゾートライクな開放感を演出できます。
また、無機質になりがちな外壁材とのコントラストも美しく、建物全体の外観を引き締めるアクセントとしても効果的です。
もちろん、木目調以外にも選択肢はあります。
シンプルでクリーンな印象を与える無地のホワイトやアイボリー、モダンでスタイリッシュな雰囲気を強調するグレーやブラックなど、ソリッドカラーの軒天も人気です。
これらは、建物のデザインをミニマルにまとめたい場合や、他のデザイン要素を引き立たせたい場合に適しています。
積水ハウスでは、これらの豊富なデザインラインナップの中から、外壁の色や素材、屋根の形状、サッシの色など、住まい全体のバランスを考慮しながら最適な軒裏デザインを提案してくれます。
ショールームや実例見学などで実際の素材感や色合いを確認し、理想の住まいにふさわしい軒裏を見つける楽しみも、家づくりの醍醐味の一つと言えるでしょう。
標準仕様とオプションで選べる軒裏の素材

積水ハウスで家を建てる際、軒裏の素材は「標準仕様」と「オプション」から選ぶことになります。
どこまでが標準で、どこからがオプションになるのかは、選択する商品シリーズや建築する地域、契約時期によっても異なるため、事前の確認が重要です。
ここでは、一般的な傾向として、それぞれの素材の特徴を解説します。
標準仕様で選ばれることが多い素材
一般的に、標準仕様として採用されることが多いのは、「ケイ酸カルシウム板(ケイカル板)」や「フレキシブルボード」といった窯業系のボードです。
これらの素材は、耐火性や耐久性、耐水性に優れており、住宅の品質を確保する上で非常に信頼性の高い建材です。
デザイン面では、表面がフラットな無地タイプが基本となり、色はホワイトやアイボリー、グレーといったベーシックなものが中心です。
シンプルでどんな外観にも合わせやすく、コストパフォーマンスにも優れているため、多くの住宅で採用されています。
機能性を重視し、コストを抑えたい場合には、標準仕様の素材でも十分な満足感が得られるでしょう。
オプションで選択可能な素材
一方、よりデザイン性にこだわりたい、高級感を演出したいという場合には、オプションの出番となります。
オプションで最も人気が高いのが、前述した「木目調」の軒天材です。
これは、ケイカル板などの基材の表面に、特殊なシートや塗装でリアルな木目を再現したもので、本物の木のような美しい見た目と、工業製品ならではの高い耐久性を両立しています。
積水ハウスでは、質感や色合いの異なる多彩な木目調デザインをオプションとして用意しており、外観デザインのアクセントとして非常に効果的です。
また、さらに上質な質感を求める場合には、本物の木材(天然木)を加工した軒天材を選ぶことも可能です。
レッドシダーなどの耐久性の高い樹種が使われることが多く、その風合いや香りは、何物にも代えがたい魅力があります。
ただし、天然木は素材自体の価格が高いことに加え、定期的な塗装メンテナンスが必要になるなど、コストと手間の両面を考慮する必要があります。
その他にも、金属系の素材(ガルバリウム鋼板など)を用いて、シャープでモダンな印象を強調する選択肢もあります。
以下の表に、標準とオプションの一般的な違いをまとめました。
| 区分 | 主な素材 | 特徴 | デザイン | コスト |
|---|---|---|---|---|
| 標準仕様 | ケイ酸カルシウム板など | 耐火性、耐久性に優れる | 無地(白、グレーなど) | 標準的 |
| オプション | 木目調ボード、天然木、金属系など | 高いデザイン性、高級感 | 木目調、天然木の風合い、金属質など多彩 | 高価になる傾向 |
最終的にどの素材を選ぶかは、デザインの好み、求める機能性、そして予算とのバランスを総合的に判断して決めることが大切です。
積水ハウスの設計士とよく相談し、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、後悔のない選択をしましょう。
軒裏が果たす外壁保護などの重要な役割
軒裏は、単にデザインのためだけに存在するわけではありません。
実は、住まいを長持ちさせるために欠かせない、非常に重要な機能的役割を担っています。
その最も大きな役割が「外壁の保護」です。
もし住宅に軒が全くないとどうなるでしょうか。
雨が降れば、屋根から伝ってきた雨水が直接外壁を濡らし、壁面は常に湿った状態に置かれます。
また、強い日差しが直接外壁に当たり、紫外線によるダメージをダイレクトに受けることになります。
こうした雨水や紫外線は、外壁の塗装を劣化させ、色褪せやひび割れ、さらにはカビや苔の発生原因となります。
外壁の劣化が進行すると、見た目が悪くなるだけでなく、建物の防水性能が低下し、構造内部への雨水の浸入を招く恐れさえあります。
ここで活躍するのが軒の存在です。
外壁から突き出た軒は、いわば建物にとっての「傘」のようなものです。
深い軒があればあるほど、雨が直接外壁にかかるのを防いでくれます。
特に、窓や玄関ドアなどの開口部周りは、雨漏りのリスクが高い場所ですが、軒があることでそのリスクを大幅に軽減できます。
同様に、夏場の厳しい直射日光が外壁や窓に当たるのを和らげる効果もあります。
これにより、外壁材の温度上昇を抑え、熱による伸縮や劣化を防ぎます。
さらに、室内に差し込む日差しをコントロールし、夏の冷房効率を高めるという省エネ効果も期待できるのです。
つまり、積水ハウスの軒裏を含む軒部分は、外壁の美観と性能を長期間維持するための「縁の下の力持ち」なのです。
この他にも、軒裏にはいくつかの重要な役割があります。
- 延焼防止効果:火災が発生した際、窓から噴き出した炎が直接屋根に燃え移るのを防ぐ役割があります。軒裏に不燃材を使用することで、さらに高い防火性能を発揮します。
- 換気機能:軒裏に換気口(軒天換気)を設けることで、屋根裏の湿気や熱気を排出し、結露の発生を防ぎます。これにより、屋根構造材の腐食を防ぎ、建物の耐久性を高めます。
- 雨仕舞い:屋根からの雨水を適切に雨樋へと導き、建物への浸水を防ぐ役割も担っています。
このように、軒裏はデザイン性だけでなく、建物の耐久性、快適性、安全性を支える多岐にわたる機能を持っています。
家づくりの際には、その機能的な側面にもぜひ注目してみてください。
高級感と耐久性を両立する軒裏の機能性

これまでの説明で、積水ハウスの軒裏が優れたデザイン性と、外壁保護をはじめとする重要な機能性を持っていることをご理解いただけたかと思います。
そして、積水ハウスが提供する軒裏の最大の魅力は、この「高級感あふれるデザイン」と「長期にわたる耐久性」という、一見すると相反する要素を見事に両立させている点にあると言えるでしょう。
例えば、オプションで人気の高い木目調の軒天材を考えてみましょう。
本物の木材を使えば、確かに比類のない高級感と温かみが得られます。
しかし、天然素材であるがゆえに、紫外線や風雨にさらされ続けることで、色褪せ、反り、腐食といった経年劣化は避けられません。
美しい状態を維持するためには、数年ごとの再塗装などの定期的なメンテナンスが必須となり、手間とコストがかかります。
一方で、積水ハウスが採用する高耐久の木目調軒天材は、工業製品ならではの緻密な技術によって作られています。
基材には耐火性・耐久性に優れた無機質なボードを使用し、その表面に、本物の木と見紛うほどリアルな木目柄を特殊な技術でコーティングしています。
このコーティング層は、耐候性・耐汚染性に非常に優れており、長期間にわたって紫外線や雨水による劣化を防ぎます。
結果として、メンテナンスの手間を大幅に削減しながら、まるで本物の木を使ったかのような上質なデザインを長く楽しむことができるのです。
これは、施主にとっては非常に大きなメリットと言えます。
家を建てた瞬間の美しさがずっと続くことは、日々の暮らしの満足度を高めるだけでなく、将来的なメンテナンスコストの削減にもつながり、資産価値の維持にも貢献します。
この「高級感」と「耐久性」の両立は、積水ハウスの長年にわたる技術開発の賜物です。
- 素材技術:基礎となるボードの性能向上。
- 加工技術:リアルな質感を再現する意匠性の追求。
- 耐久技術:美しさを長持ちさせるためのコーティング技術。
これらの技術が組み合わさることで、施主はデザインの選択を妥協することなく、かつ将来の心配も少ない、理想的な住まいを実現できます。
軒裏という細部にまで、美しさと強さを追求する姿勢こそが、積水ハウスが多くの人々に選ばれ続ける理由の一つなのかもしれません。
初期コストは多少上がったとしても、長期的な視点で見れば、この「高級感と耐久性の両立」は非常に価値のある投資と言えるでしょう。
\300万円以上の値引き実績あり!/
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
失敗しない積水ハウスの軒裏選びと設計のポイント
- 知っておきたい軒裏のデメリットと対策
- 屋根材との組み合わせで変わる家の雰囲気
- 軒裏設計で後悔しないための注意点
- 気になる軒裏のオプション費用について
- 美観を保つためのメンテナンス方法
- 満足のいく積水ハウスの軒裏にするために
知っておきたい軒裏のデメリットと対策

積水ハウスの軒裏はデザイン性・機能性ともに多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットや注意点も存在します。
これらを事前に理解し、対策を講じることで、後悔のない家づくりにつながります。
コストが増加する可能性がある
最も分かりやすいデメリットは、費用面の負担です。
特に、デザイン性の高い木目調の軒天材や天然木、金属系素材などをオプションで選択した場合、標準仕様に比べてコストは確実に増加します。
軒の面積が広ければ広いほど、その差額は大きくなります。
【対策】
対策としては、まず「こだわりたい場所」と「そうでない場所」を明確にすることが重要です。
例えば、人目に付きやすい玄関ポーチやリビングから見える部分だけをオプションの木目調にし、それ以外の部分は標準仕様にするといった「使い分け」を検討することで、コストを抑えつつデザイン性を高めることが可能です。
また、家全体の予算を考慮し、軒裏にかけられる費用の上限をあらかじめ設計士に伝えておくことも大切です。
日当たりが悪くなる場合がある
軒を深くすると、夏の強い日差しを遮るという大きなメリットがありますが、逆に冬場には室内に太陽光が入りにくくなる可能性があります。
特に、南側に大きな窓を設ける場合、深い軒が日照を妨げ、部屋が暗く感じられたり、暖房効率が低下したりするケースも考えられます。
【対策】
積水ハウスの設計士は、敷地の条件や太陽の動きを計算した上で、最適な軒の出(深さ)を提案してくれます。
夏の高い太陽光は遮りつつ、冬の低い太陽光は室内に取り込めるような、絶妙な長さに設計することが可能です。
シミュレーションなどを通じて、一年を通した日当たりの変化を確認させてもらうと良いでしょう。
鳥や虫の巣作りの場所になる可能性
軒裏は雨風をしのげるため、鳥や蜂、クモなどが巣を作る格好の場所になり得ます。
特に、軒天と外壁の取り合い部分や換気口の周りなどは注意が必要です。
巣が作られると、フンによる汚れや、蜂に刺されるといった衛生面・安全面での問題が発生します。
【対策】
対策としては、まず物理的に巣を作りにくい構造にすることが考えられます。
隙間ができないような丁寧な施工はもちろんのこと、防鳥ネットや虫が侵入しにくい構造の換気口を採用するといった方法があります。
また、定期的に軒下を点検し、巣が作られ始めていないかチェックする習慣をつけることも有効です。
これらのデメリットは、いずれも適切な設計と事前の対策によって十分にカバーできるものです。
不安な点があれば、遠慮なく設計士に質問し、納得のいく答えを得てから計画を進めるようにしましょう。
屋根材との組み合わせで変わる家の雰囲気
軒裏のデザインを考える際、単体で選ぶのではなく、必ず「屋根材」との組み合わせを意識することが重要です。
軒裏は屋根の一部であり、屋根材との色や質感の調和がとれていないと、ちぐはぐで落ち着きのない外観になってしまうからです。
積水ハウスで選べる屋根材には、主に以下のような種類があります。
- スレート(コロニアル、カラーベスト):薄い板状のセメント系の屋根材で、フラットな見た目が特徴。モダンでシンプルな住宅によく合います。カラーバリエーションが豊富です。
- 瓦(陶器瓦、セメント瓦):日本の伝統的な屋根材。重厚感と高級感があり、和風や洋風のデザインにも対応できます。耐久性が非常に高いのが魅力です。
- 金属屋根(ガルバリウム鋼板):軽量で耐久性が高く、シャープでスタイリッシュな印象を与えます。近年、モダンなデザインの住宅で人気が高まっています。
これらの屋根材と軒裏をどのように組み合わせると、どのような雰囲気が生まれるのか、いくつかの例を見てみましょう。
スレート屋根との組み合わせ
フラットでシンプルなスレート屋根には、同じくシンプルですっきりとした軒裏がよく合います。
例えば、ダークグレーのスレート屋根に、ホワイト系の無地の軒裏を合わせると、コントラストが効いたモダンな印象になります。
ここに、アクセントとして木目調の軒裏を部分的に採用すると、無機質な印象が和らぎ、温かみがプラスされます。
瓦屋根との組み合わせ
重厚感のある瓦屋根の場合、軒裏にもある程度の存在感が求められます。
例えば、いぶし銀の和瓦には、格調高い雰囲気を持つ濃い色の木目調の軒裏が非常にマッチします。
これにより、本格的な和風建築のような風格を演出できます。
一方、南欧風の洋瓦(オレンジやブラウン系)には、少し明るめの木目調や、漆喰のような質感を持つオフホワイトの軒裏を合わせると、リゾート感あふれる明るい雰囲気が生まれます。
金属屋根との組み合わせ
シャープなラインが特徴の金属屋根には、軒裏もモダンな素材で統一すると、洗練された印象が際立ちます。
ブラックやシルバーの金属屋根に、同系色の軒裏を組み合わせることで、建物全体がシャープな塊(マッス)として見え、非常にスタイリッシュです。
あえてここに濃い色の木目調を合わせる「異素材ミックス」も人気で、インダストリアルデザインのようなクールさと温かみを両立させることができます。
このように、屋根材と軒裏の組み合わせは無限にあり、それによって家の表情は大きく変わります。
外壁の色や素材も含めた全体のカラーパレットを考え、統一感のあるコーディネートを心がけることが、美しい外観デザインを成功させる秘訣です。
積水ハウスのカラーシミュレーションなどを活用して、様々な組み合わせを試してみることをお勧めします。
軒裏設計で後悔しないための注意点

理想のマイホームを実現するため、軒裏の設計においても後悔はしたくないものです。
デザインや素材選びに加えて、設計段階で注意しておくべきいくつかのポイントがあります。
これらを事前に押さえておくことで、住み始めてからの「こんなはずではなかった」を防ぐことができます。
軒の出(深さ)を慎重に検討する
軒の出の長さは、外観の印象だけでなく、機能性にも直結する重要な要素です。
軒が深いと、重厚感が出て雨や日差しを防ぐ効果が高まりますが、前述の通り、冬の日当たりが悪くなる可能性があります。
逆に軒が浅い、あるいは全くないと、モダンでシンプルな外観になりますが、外壁が汚れやすくなったり、夏の室温が上がりやすくなったりします。
【注意点】
デザインの好みだけで決めず、必ず機能面とのバランスを考慮しましょう。
特に、土地の方角や周辺の建物の状況によって、最適な軒の出は変わってきます。
設計士に敷地ごとの日照シミュレーションを依頼し、夏と冬の日差しの入り方を具体的に確認した上で決定することが、後悔しないための最善策です。
軒天換気の有無と種類を確認する
軒裏には、屋根裏の湿気を排出するための換気口が設けられることが多くあります。
この軒天換気は、建物の耐久性を保つ上で非常に重要です。
しかし、換気口のデザインによっては、外観のイメージに影響を与える場合があります。
【注意点】
換気が必要な場合、どのようなタイプの換気口がどこに取り付けられるのかを、設計図で必ず確認しましょう。
最近では、スリット状で目立たないデザインの換気口など、意匠性を損なわない製品も増えています。
特に、軒裏全体をすっきりとした一枚の面として見せたい場合は、換気口のデザインや配置に配慮が必要です。
照明計画を同時に進める
玄関ポーチやウッドデッキの上の軒裏には、ダウンライトなどの照明を設置することが一般的です。
この照明計画を、軒裏の素材やデザインを決めるのと同時に進めることが大切です。
【注意点】
例えば、木目調の軒裏に照明を埋め込む場合、照明器具の縁の色が目立たないか、光の広がり方が木目のデザインと合っているかなどを考慮する必要があります。
後から「ここに照明を追加したい」と思っても、配線工事が大がかりになる場合があります。
夜間の外観の雰囲気や、足元の明るさなどをイメージしながら、必要な場所に必要な数の照明を計画的に配置しましょう。
実物サンプルで色や質感を確認する
カタログや画面上で見る色と、実際の素材の色や質感は、光の当たり方によって印象が異なることがよくあります。
小さなサンプルで見たときと、広い面積に施工されたときとで、イメージが違うというのもよくある話です。
【注意点】
契約前に、できるだけ大きなサンプルを取り寄せてもらい、屋外の自然光の下で確認することをお勧めします。
可能であれば、同じ軒裏材を使用している建築中の現場や、完成物件を見学させてもらうのが最も確実です。
外壁材やサッシのサンプルと並べて、全体のバランスを確認する作業も忘れないようにしましょう。
気になる軒裏のオプション費用について
積水ハウスの軒裏で、デザイン性の高い木目調などを選ぶ場合、やはり気になるのがオプション費用です。
具体的な金額は、選択する素材、施工面積、建物の形状などによって大きく変動するため、一概に「いくら」と示すことは難しいのが実情です。
しかし、費用の考え方や価格に影響する要因を理解しておくことは、予算計画を立てる上で非常に役立ちます。
費用を左右する主な要因
軒裏のオプション費用は、主に以下の要素によって決まります。
- 素材の種類:最も大きな要因は素材のグレードです。一般的に「標準の無地ボード < 木目調ボード < 天然木」の順に価格は高くなります。
- 施工面積:当然ながら、軒裏の面積が広ければ広いほど、材料費も施工費も増加します。軒の出が深いデザインや、総二階ではなく一階部分に屋根が多いプランなどは、軒裏面積が大きくなる傾向があります。
- 建物の形状:シンプルな長方形の建物よりも、凹凸の多い複雑な形状の建物の方が、軒裏の施工に手間がかかるため、施工費が割高になる可能性があります。
費用感の目安
あくまで一般的な目安ですが、標準仕様の無地ボードから、人気の木目調ボードにオプション変更した場合、家全体で数十万円の追加費用が発生するケースが多いようです。
例えば、30坪程度の一般的な住宅で、軒裏全体の面積が30平方メートルあったとします。
標準材とオプション材の差額が1平方メートルあたり数千円だとしても、全体では10万円以上の差になる計算です。
これが全面ではなく、アクセントとして玄関ポーチ部分(例えば5平方メートル)だけを変更するのであれば、数万円程度の追加で済むかもしれません。
より具体的な金額を知るためには、希望する仕様を設計士に伝えた上で、正式な見積もりを取得することが不可欠です。
「この木目調にした場合はいくらプラスになりますか?」と、パターン別の見積もりを依頼すると、比較検討しやすくなります。
コストを抑える工夫
予算に限りがある中で、できるだけ理想のデザインを実現するためには、いくつかの工夫が考えられます。
- 部分採用:前述の通り、玄関やウッドデッキなど、こだわりたい部分に限定してオプションを採用する。
- グレードの検討:木目調の中でも、複数のグレードが用意されている場合があります。デザインの好みが合えば、少し下のグレードを選ぶことでコストを抑えられる可能性があります。
- 軒の出の調整:デザイン上、問題がなければ、軒の出を少し浅くすることで軒裏の面積を減らし、コストを削減するという考え方もあります。ただし、機能性とのバランスは慎重に検討する必要があります。
オプション費用は、家づくり全体の予算から見れば一部かもしれませんが、積み重なると大きな金額になります。
どこにコストをかけ、どこを削るのか、優先順位を明確にして、賢くオプション選びをすることが、満足度の高い家づくりにつながります。
美観を保つためのメンテナンス方法

せっかくこだわって選んだ積水ハウスの軒裏ですから、できるだけ長く美しい状態を保ちたいものです。
積水ハウスが採用する軒天材は、耐久性の高いものが多いため、頻繁なメンテナンスは基本的に不要です。
しかし、全く何もしなくて良いというわけではありません。
適切な時期に簡単な手入れを行うことで、美観を損なうことなく、建物の寿命を延ばすことにもつながります。
日常的なチェックと清掃
日常的にできる最も簡単なメンテナンスは、「目視でのチェック」です。
庭の手入れをする際や、洗車のついでなどに、軒裏を見上げてみましょう。
- 汚れやクモの巣:軒裏には、風で運ばれてきた土埃が付着したり、クモが巣を張ったりすることがあります。これらは美観を損なう原因になります。
- 鳥の巣やフン:鳥が巣を作っていないか、フンで汚れていないかを確認します。
- 変色や剥がれ:万が一、塗装の剥がれや目立つ変色がないかをチェックします。
軽い汚れやクモの巣であれば、柄の長い柔らかいブラシやほうきで優しく払うだけで簡単に取り除けます。
手が届く範囲であれば、固く絞った雑巾で水拭きするのも良いでしょう。
ただし、高圧洗浄機を直接軒裏に当てるのは避けてください。
水の勢いで素材を傷めたり、換気口から水が浸入したりする恐れがあります。
定期的な専門家による点検
積水ハウスでは、引き渡し後も定期的な点検サービスを実施しています。
専門のスタッフが、屋根や外壁と合わせて軒裏の状態もチェックしてくれます。
普段目の届かないような場所や、自分では判断が難しい劣化のサインなども、プロの視点で確認してもらえるため非常に安心です。
もし点検で何らかの異常が見つかった場合は、その指示に従って適切な処置を依頼しましょう。
早期発見・早期対応が、結果的に補修費用を安く抑えることにつながります。
素材別のメンテナンス注意点
選択した素材によって、メンテナンスのポイントが若干異なります。
- 窯業系ボード(無地・木目調):基本的にメンテナンスフリーに近い素材ですが、継ぎ目部分のシーリング材は、経年で劣化することがあります。定期点検でシーリングの状態を確認してもらい、必要であれば補修(打ち替え)を行います。
- 天然木:最もメンテナンスが必要な素材です。数年から10年程度で、保護塗料の再塗装が必要になります。塗装が劣化すると、木の腐食や変色の原因となるため、適切なタイミングでメンテナンスを行いましょう。
軒裏のメンテナンスは、足場が必要になる場合もあり、個人で行うのは危険を伴います。
基本的な清掃以外は、無理をせず積水ハウスのアフターサービスや専門の業者に相談することをお勧めします。
日頃のちょっとした心がけと、定期的なプロのチェックを組み合わせることで、自慢の軒裏の美しさを末永く保つことができるでしょう。
満足のいく積水ハウスの軒裏にするために
これまで、積水ハウスの軒裏が持つデザインの魅力、住まいを守る機能性、そして後悔しないための選び方や注意点について詳しく解説してきました。
軒裏は、家全体の印象を決定づける重要なデザイン要素でありながら、外壁の劣化を防ぎ、建物の耐久性を高めるという実用的な役割も担っています。
この両側面を深く理解することが、満足のいく軒裏選びの第一歩となります。
積水ハウスでは、シンプルな標準仕様から、高級感あふれる木目調のオプションまで、多岐にわたる選択肢が用意されています。
それぞれの素材が持つメリット・デメリット、そして費用感を把握した上で、ご自身のライフスタイルや価値観、そして家全体のデザインコンセプトに最も合ったものを選ぶことが大切です。
「玄関周りだけは、こだわりの木目調にして、訪れる人をおしゃれにお迎えしたい」
「メンテナンスの手間を考えて、とにかく耐久性の高い素材を選びたい」
「屋根や外壁とのトータルバランスを重視して、統一感のあるすっきりとした外観にしたい」
どのような家にしたいのか、その理想のイメージを明確にし、設計士と共有することで、提案の精度もより高まります。
本記事でご紹介した、軒の出の長さや照明計画、換気口の確認といった設計上の注意点も、ぜひ打ち合わせの際に役立ててください。
小さな疑問や不安も、その都度解消していくことが、後悔のない家づくりへの近道です。
最終的に選ばれた積水ハウスの軒裏は、単なる建築部材ではなく、あなたの家の個性を象徴し、家族の暮らしを静かに見守り続ける存在となるでしょう。
この記事が、そのための最良の選択をする一助となれたなら、これほど嬉しいことはありません。
- 積水ハウスの軒裏はデザイン性と機能性を両立している
- 軒裏のデザインは家の外観印象を大きく左右する重要な要素
- 人気の木目調は温かみと高級感を演出し種類も豊富
- 軒裏の役割は雨や紫外線から外壁を保護し劣化を防ぐこと
- 軒の深さは夏の日差しを遮り冬の日差しを取り込む設計が可能
- 標準仕様は主にケイカル板で機能的かつ経済的
- オプションでは木目調や天然木など多彩なデザインが選べる
- オプション選択時は家全体で数十万円の費用増が目安
- コストを抑えるには玄関周りなどへの部分採用が効果的
- デメリットとしてコスト増や日当たりの変化が挙げられる
- 鳥や虫の巣対策も設計段階で考慮すべきポイント
- 屋根材との色や素材の組み合わせで家の雰囲気が決まる
- 設計時には軒の出の長さや換気口、照明計画も要確認
- サンプルは自然光の下で確認し完成物件の見学も有効
- メンテナンスは基本的に不要だが定期的なチェックで美観を維持

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、
自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。
そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。
気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼
▼オリジナル間取りプランの例▼
『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓
- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい
- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い
- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい






















