
ヘーベルハウスの床下に関心を持つ方は多く、特にその床下構造や耐久性について詳しく知りたいと考えているのではないでしょうか。
ヘーベルハウスは独自の床下構造を採用し、高い耐震性や耐火性を実現しています。
また、床下点検口を各部屋に設置し、定期的な点検を行いやすくすることで、長期間にわたる住宅のメンテナンス性を向上させています。
さらに、床下浸水に強い設計が施されており、万が一の水害時にも被害を最小限に抑えられる点が特徴です。
防湿対策としては、基礎部分に防湿シートを敷くことで湿気の影響を軽減し、カビや腐食を防ぐ工夫がされています。
加えて、高性能断熱材を使用することで、床構造の断熱性も向上し、快適な室内環境を維持しやすくなっています。
本記事では、ヘーベルハウスの床下に関する詳細な情報を解説し、床下の構造やメンテナンス方法、防湿・耐水対策など、快適な住まいを維持するためのポイントを紹介します。
ヘーベルハウスの家を検討している方や、すでに住んでいる方にとって、役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
- ヘーベルハウスの床下構造の特徴やメリットが理解できる
- 床下点検口の役割と定期点検の重要性がわかる
- 床下浸水に強い理由とその対策について学べる
- 防湿シートの必要性と基礎部分の湿気対策を知れる
- 床下の断熱性能や冷え対策について理解できる
- 重い家具を置く際の耐荷重や床の補強方法がわかる
- メンテナンス費用やコストを抑える工夫について学べる
\300万円以上の差がつく/
複数社比較の相見積もりは
やらないと損!!
▼3分で完了!希望条件を入力するだけ▼
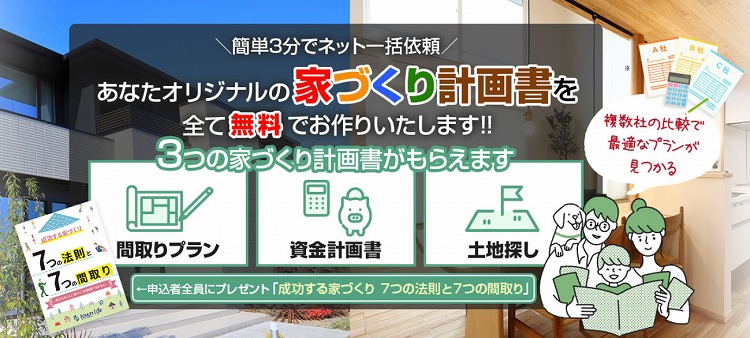 1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
1,170社以上(大手36社を含む)の優良ハウスメーカーを掲載、運営歴12年、累計利用者40万人の実績!
「間取りプラン」「見積もり」「土地探し」3つの計画書を希望の複数企業から無料で貰える!
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼

『タウンライフ家づくり』は40万人以上が利用した大手サイトなので安心です
希望の条件を入力するだけ!たった3分で申し込みが完了、手数料も必要ナシ
さらに家づくりを失敗したくない人は必読の『成功する家づくり 7つの法則と7つの間取り』のプレゼントも貰える!
▼成功する家づくりプレゼント▼
- 希望の家の質問に回答(約3分)
- ハウスメーカーを選択(複数可)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
ヘーベルハウスの床下構造とは?耐久性とメンテナンスのポイント
-
ヘーベルハウスの床下の特徴と強み
-
床下の構造と採用されている素材
-
床下点検口の設置理由とその役割
-
床下の防湿対策|防湿シートの必要性
-
床下浸水に強い理由|ALCコンクリートと基礎設計
ヘーベルハウスの床下の特徴と強み

ヘーベルハウスの床下は、耐久性・耐震性・耐火性の三つの観点で優れた特徴を持っています。
その最大の特徴は、ALCコンクリート(軽量気泡コンクリート)を床材として使用している点にあります。
一般的な木造住宅の床下とは異なり、ALCコンクリートを採用することで、強度が増し、シロアリ被害や湿気による劣化のリスクを低減できます。
また、床下の構造として基礎部分に「連続布基礎」を採用しているため、地盤全体に建物の荷重を分散しやすく、安定した住宅基盤を提供できます。
耐震性能に関しても、鉄骨構造と組み合わせることで、揺れに対して強く、災害時の被害を最小限に抑える工夫がされています。
さらに、防火性能についても、ALCコンクリートの特性上、高い耐火性能を持ち、火災の延焼を防ぐ効果があります。
これにより、住宅密集地や火災リスクの高いエリアでも安心して住める住宅を提供できます。
ただし、ALCコンクリートは一般的な木造住宅の床材と比較すると冷えやすい傾向があります。
そのため、適切な断熱対策が必要であり、床暖房の導入などで快適な住環境を整える工夫が求められます。
こうしたヘーベルハウスの床下の特徴は、長期間にわたって安全で快適な住まいを実現するための設計思想に基づいています。
【関連】ヘーベルハウス公式
床下の構造と採用されている素材

ヘーベルハウスの床下構造は、一般的な住宅とは異なり、耐久性を重視した設計がなされています。
最も大きな特徴は、「ALCコンクリート(軽量気泡コンクリート)」が採用されている点です。
この素材は、一般的なコンクリートよりも軽量でありながら、高い強度と断熱性を兼ね備えています。
また、ALCコンクリートは水に強く、湿気を通しにくいため、カビや腐食のリスクを低減できます。
さらに、ヘーベルハウスでは「連続布基礎」と呼ばれる基礎構造を採用しています。
これは、一般的なベタ基礎とは異なり、基礎の中に通気層を確保することで、床下の湿気を効率的に排出できるよう設計されています。
これにより、床下の換気性が高まり、建物の耐久性が向上します。
また、ヘーベルハウスの床下には、高性能断熱材「ネオマフォーム」が使用されています。
この断熱材は、熱伝導率が非常に低く、優れた断熱性能を持っています。
ただし、床下の冷えを完全に防ぐわけではないため、必要に応じて追加の断熱対策や床暖房の導入を検討するのが望ましいです。
これらの素材と構造を組み合わせることで、ヘーベルハウスの床下は、耐久性・耐震性・防火性・断熱性に優れたものとなっています。
床下点検口の設置理由とその役割
ヘーベルハウスでは、1階の各部屋に床下点検口を設置する仕様が採用されています。
この点検口の設置には、住宅の長期的なメンテナンス性を向上させる目的があります。
まず、床下点検口を設けることで、給排水管や電気配線、シロアリ被害の有無などを定期的に点検することができます。
これにより、配管の劣化や漏水の兆候を早期に発見し、修理や交換を迅速に行うことが可能になります。
また、ヘーベルハウスの連続布基礎構造では、各部屋ごとに床下が区画されているため、従来のベタ基礎のように一箇所の点検口から全体を確認することができません。
そのため、各部屋に点検口を設けることで、適切なメンテナンスができるように工夫されています。
加えて、床下点検口は、シロアリ対策にも活用されます。
通常、シロアリ被害は床下から発生することが多いため、定期的な点検が欠かせません。
この点検口を利用することで、シロアリの侵入や被害の進行を早期に発見し、対策を講じることができます。
ただし、点検口が多くなることで、断熱性に影響を与える可能性があります。
そのため、点検口の蓋には断熱材が使用されているか、追加の断熱対策が必要になる場合があります。
このように、床下点検口の設置は、長期的な住宅の維持管理を考慮した重要な要素であり、定期的な点検を行うことで、より快適で安全な住環境を維持することが可能になります。
床下の防湿対策|防湿シートの必要性

ヘーベルハウスでは、床下の防湿対策としてさまざまな工夫が施されています。
住宅の耐久性を高めるためには、床下の湿気対策が重要です。
床下に湿気が溜まると、カビの発生や木材の腐食、シロアリ被害のリスクが高まります。
このような問題を防ぐため、一般的な住宅では「防湿シート」が使用されることが多いですが、ヘーベルハウスでは異なるアプローチが取られています。
ヘーベルハウスの床下は「ALCコンクリート(軽量気泡コンクリート)」を採用しており、これが防湿性能の向上に大きく貢献しています。
ALCコンクリートは非常に細かい気泡を含んでおり、一般的なコンクリートと比較して水を通しにくい特徴があります。
そのため、湿気が床下に侵入するのを防ぎ、住宅全体の耐久性を向上させることができます。
また、ヘーベルハウスでは「連続布基礎」を採用しており、床下の通気性を確保する設計がされています。
これにより、湿気がこもるのを防ぎ、常に乾燥した状態を維持しやすくなっています。
一般的な木造住宅では、床下の通気口を設けて湿気を逃がしますが、ヘーベルハウスでは基礎自体が通気性を確保する構造になっているため、特別な防湿シートを敷く必要がありません。
ただし、地域によっては地盤の性質や気候条件によって湿気が多く発生する場合があります。
そのため、地盤が軟弱で湿気が多い地域では、防湿シートを敷くことが推奨されるケースもあります。
施工の段階で地盤の状態を確認し、必要に応じて防湿シートを追加することで、さらなる湿気対策を行うことができます。
また、定期的な点検を行い、床下の湿気が過剰になっていないか確認することも重要です。
もし湿気が多い場合は、床下の換気システムを見直す、追加の防湿シートを敷くなどの対策を取ることができます。
以上のように、ヘーベルハウスでは防湿シートを使用しなくても高い防湿性能を発揮する設計がされていますが、地域や状況に応じた追加の対策を行うことで、より安心して住める環境を作ることができます。
床下浸水に強い理由|ALCコンクリートと基礎設計
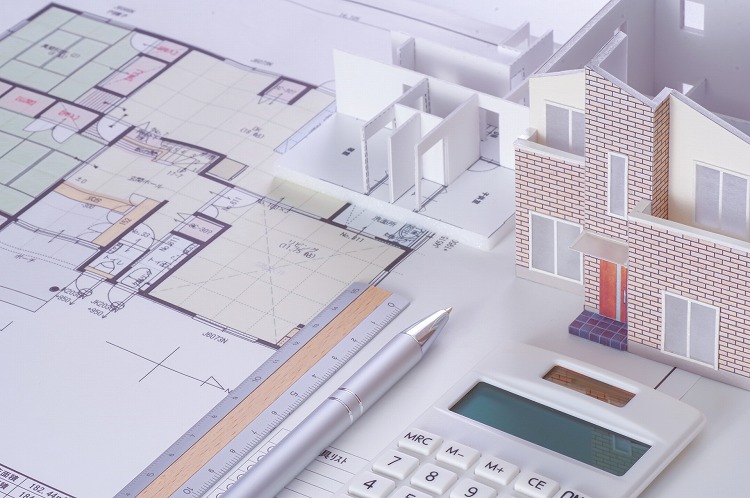
ヘーベルハウスは、一般的な住宅と比べて床下浸水に強い構造を持っています。
その理由は、大きく分けて「ALCコンクリートの特性」と「基礎設計の工夫」にあります。
まず、ヘーベルハウスの床材として使用されている「ALCコンクリート(軽量気泡コンクリート)」は、水に強い素材です。
ALCコンクリートは内部に細かい気泡を含んでおり、水を吸収しにくい性質を持っています。
これにより、万が一床下が浸水しても、水を吸い込んで劣化することがなく、乾燥すれば元の状態に戻るという特徴があります。
一般的な木造住宅では、床下が浸水すると木材が水を吸収して腐敗しやすくなりますが、ヘーベルハウスのALCコンクリートならその心配がほとんどありません。
次に、基礎設計に関する工夫です。
ヘーベルハウスでは「連続布基礎」を採用しています。
この基礎構造は、一般的なベタ基礎とは異なり、床下に空間を持たせる設計になっています。
この空間があることで、万が一浸水しても水が自然に排出されやすくなり、湿気がこもるのを防ぐことができます。
さらに、ヘーベルハウスの基礎は鉄筋コンクリートで作られており、耐水性が高いため、浸水した際のダメージを最小限に抑えることができます。
また、床下点検口が各部屋に設置されているため、浸水後の点検やメンテナンスも比較的容易に行うことができます。
この設計により、万が一の床下浸水が発生しても、被害を最小限に抑え、迅速に復旧することが可能です。
一方で、ヘーベルハウスの基礎構造は高い耐水性を誇るものの、完全に浸水を防げるわけではありません。
そのため、浸水リスクの高い地域では、事前に「かさ上げ工事」を行ったり、排水機能を強化することが推奨されます。
また、床下浸水のリスクがある場合は、定期的な点検を行い、排水の流れがスムーズかどうかを確認することも重要です。
こうした設計と対策により、ヘーベルハウスは床下浸水に対して強い耐性を持ち、万が一の水害にも迅速に対応できる住宅となっています。
都市部や低地に建築を予定している方にとっては、こうした防水・耐水性能の高さは大きな安心材料となるでしょう。
\300万円以上の値引き実績あり!/
- 家づくりアンケート回答(約3分)
- 希望のハウスメーカーを選択(1,170社以上から)
- 無料で間取りと見積もりが届く!
ヘーベルハウスの床下メンテナンスとコストを抑える方法
-
床下点検の頻度とチェックポイント
-
シロアリ対策|防蟻処理は必要か?
-
床下の断熱性能|冷えやすい?暖かい?
-
重い家具で床が沈む?床構造の耐荷重とは
-
床材の選び方|フローリング・タイル・カーペットの違い
-
ヘーベルハウスの床下メンテナンス費用はどれくらい?
-
ヘーベルハウスの床下をより快適にするための工夫
床下点検の頻度とチェックポイント

ヘーベルハウスの床下点検は、住宅の長期的な安全性と快適性を維持するために非常に重要です。
一般的に、床下の点検は10年ごとの定期点検が推奨されていますが、ヘーベルハウスではより長期間にわたり、無料点検サービスを提供しています。
定期点検を行うことで、給排水管の劣化やシロアリ被害、湿気の蓄積などの問題を早期に発見し、修理費用を抑えることができます。
特にヘーベルハウスの床下は「連続布基礎」という特殊な構造になっており、各部屋ごとに区画されているため、一般的な住宅のように一箇所の点検口から全体をチェックすることができません。
そのため、各部屋に設けられた床下点検口を活用し、各エリアの状況を確認することが重要です。
点検の際には、以下のようなチェックポイントを押さえておくと良いでしょう。
- 湿気やカビの発生:ヘーベルハウスの床下は湿気に強い構造になっていますが、気候や地域によっては湿気が溜まりやすい場所もあります。
- 給排水管の劣化や水漏れ:水漏れは床下の腐食やカビの発生を招くため、定期的に確認することが必要です。
- シロアリや害虫の侵入:ALCコンクリートを使用しているためシロアリの被害は少ないですが、完全にゼロとは言い切れません。
- 基礎部分のひび割れや変形:耐震性が高い構造ですが、経年劣化により小さなひび割れが発生する可能性があります。
定期点検は専門の業者やヘーベルハウスの無料点検サービスを利用するのが最も確実ですが、自分でも点検口から懐中電灯を使って簡単な確認を行うことで、異変を早期に察知することができます。
万が一、異常が見つかった場合は、早めに専門業者に相談し、適切な対策を講じることが大切です。
シロアリ対策|防蟻処理は必要か?
ヘーベルハウスはALCコンクリート(軽量気泡コンクリート)を使用しているため、一般的な木造住宅と比べるとシロアリの被害を受けにくい構造になっています。
しかしながら、完全にシロアリのリスクがゼロになるわけではなく、特に床下の木材部分や断熱材には注意が必要です。
シロアリの主な侵入経路は、基礎部分の隙間や給排水管の周辺、断熱材の中です。
一般的な住宅では、シロアリ対策として防蟻処理を施すことが多いですが、ヘーベルハウスでは木材の使用量が少ないため、大掛かりな防蟻処理は不要とされています。
ただし、シロアリ被害を未然に防ぐために、以下の対策を検討することが推奨されます。
- 定期的な床下点検を行う:シロアリは目に見えない場所で活動するため、床下の点検を怠ると被害が進行してしまいます。
- 床下の換気を確保する:湿気が多い環境はシロアリが好むため、換気状態を良好に保つことが重要です。
- 基礎部分のシーリングや隙間をチェックする:給排水管の通り道に隙間があると、そこからシロアリが侵入する可能性があります。
- 木材部分に防蟻処理を施す:床下の木材や玄関周りなど、シロアリの侵入リスクが高い部分には、専用の防蟻剤を塗布することで対策できます。
シロアリ被害のリスクは、地域や気候によって異なります。
特に湿気が多く、シロアリが発生しやすい地域では、防蟻処理を定期的に行うことが有効な対策となります。
また、ヘーベルハウスでは30年の長期保証が提供されており、保証期間内であれば、万が一シロアリの被害が発生した場合でも適切な修理対応を受けることができます。
シロアリ被害を未然に防ぐためには、定期的な点検と、必要に応じた防蟻処理を行うことが大切です。
床下の断熱性能|冷えやすい?暖かい?

ヘーベルハウスの床下は、ALCコンクリートを使用しているため、耐久性や防火性に優れていますが、一般的な木造住宅と比べると冷えやすいと感じることがあります。
その理由は、ALCコンクリートが断熱性を持つ一方で、熱を蓄えにくい性質があるためです。
そのため、冬場には床が冷たく感じやすく、特にフローリングを採用している場合は足元の冷えを強く感じることがあります。
この問題に対処するため、ヘーベルハウスでは高性能断熱材「ネオマフォーム」を床下に採用しています。
ネオマフォームは、従来の断熱材と比較して高い断熱性能を誇り、熱伝導率が低いため、床下の冷気を軽減する効果があります。
ただし、床下の断熱性をさらに向上させるためには、以下のような追加対策を行うことが効果的です。
- 床暖房の導入:ヘーベルハウスでは床暖房をオプションとして選択でき、特に冬場の快適性が向上します。
- カーペットやラグを活用する:フローリングの場合、床が直接冷えるため、カーペットやラグを敷くことで体感温度を上げることができます。
- 室内の温度管理を徹底する:全館空調システムを導入すると、家全体の温度を均一に保つことができ、床の冷えを抑えることが可能です。
また、床下の断熱性能を考える際には、地域の気候も考慮する必要があります。
寒冷地では、さらに厚みのある断熱材を追加したり、床暖房を積極的に取り入れることで、快適な住環境を実現することができます。
一方で、夏場の床下の断熱性能も重要です。
ヘーベルハウスでは、ALCコンクリートとネオマフォームの組み合わせにより、外部からの熱の侵入を抑える効果があります。
そのため、夏は室内の温度を一定に保ちやすく、冷房の効率を高めることができます。
結論として、ヘーベルハウスの床下は耐久性や防火性に優れている一方で、冷えやすいという特性がありますが、適切な断熱材の使用や追加の暖房設備を導入することで、快適な住環境を実現することが可能です。
床暖房やカーペットの活用など、自分の生活スタイルに合わせた工夫をすることで、冬場の冷え対策を万全にすることができます。
重い家具で床が沈む?床構造の耐荷重とは
ヘーベルハウスの床構造は、ALCコンクリート(軽量気泡コンクリート)を使用しており、一般的な木造住宅と比較して耐荷重性に優れています。
ALCコンクリートは軽量でありながら高い強度を誇り、長期間にわたって安定した性能を維持することが可能です。
しかし、重い家具を設置する場合、床が沈む可能性が気になる方も多いでしょう。
ヘーベルハウスの床は、ALCコンクリートの上に断熱材やフローリングを重ねた構造になっています。
このため、一般的な家庭用家具や家電を設置する分には問題なく、床が沈むことはほとんどありません。
しかし、一部のケースでは、長期間にわたって重量がかかることで、フローリングの表面に若干の凹みが生じることがあります。
特に、冷蔵庫やピアノ、大型の本棚など、100kgを超える重量物を置く場合には、荷重の分散を考慮することが重要です。
例えば、重量が集中しやすい家具の脚部分には、耐荷重パッドや分散用の板を敷くことで、局所的な圧力を軽減することができます。
また、フローリングの種類によっては、衝撃や荷重に対する耐久性が異なります。
突板フローリングや挽板フローリングは比較的柔らかく、長期間荷重がかかると凹みやすい傾向にあります。
一方で、タイルやカーペット素材は比較的耐久性が高く、重量物による影響を受けにくいという特徴があります。
ヘーベルハウスでは、建築時に「どのような家具を配置するか」を設計士と相談し、必要に応じて補強対策を行うことも可能です。
例えば、床下の補強を施すことで、大型家具や重量のあるアイテムを設置する際の沈み込みを防ぐことができます。
また、床下点検口を活用して、施工後に追加補強を施すことも可能です。
耐荷重性能に優れたヘーベルハウスの床ですが、適切な対策を講じることで、より安心して長く使用することができます。
特に、大型の家具を置く予定がある場合は、荷重分散の工夫や補強の相談を建築時にしておくことをおすすめします。
床材の選び方|フローリング・タイル・カーペットの違い

ヘーベルハウスでは、床材の選択肢が豊富に用意されており、住まいのデザインや使用用途に応じて最適な素材を選ぶことが可能です。
床材は見た目の印象だけでなく、耐久性、メンテナンス性、断熱性能にも大きな影響を与えます。
ここでは、代表的な床材としてフローリング・タイル・カーペットの特徴を比較しながら、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
フローリングの特徴
フローリングは、ヘーベルハウスの標準仕様として最も多く採用されている床材の一つです。
素材にはシートフローリング、突板フローリング、挽板フローリング、無垢フローリングがあり、それぞれ異なる特性を持っています。
メリット
- 見た目が高級感のある仕上がりになる
- 掃除がしやすく、メンテナンスが比較的容易
- 床暖房との相性が良い
デメリット
- 冬場は冷たく感じやすい
- 傷がつきやすく、重い家具を置くと凹みが発生することがある
- 防音性が低いため、足音が響きやすい
ヘーベルハウスのフローリングは、耐久性の高いシートフローリングや突板フローリングが標準仕様となっており、デザインとメンテナンス性を両立させています。
しかし、防音性や冷え対策を考慮する場合は、カーペットやタイルの併用も検討すると良いでしょう。
タイルの特徴
タイルは、耐久性と高級感を重視したい方におすすめの床材です。
特に、玄関・キッチン・水回りなど、水に強い場所での使用に適しています。
メリット
- 耐水性が高く、水に濡れても劣化しにくい
- 傷がつきにくく、耐久性に優れている
- 高級感のあるデザインが可能
デメリット
- 冬場は特に冷たく、素足で歩くと寒さを感じる
- 硬いため、転倒時の衝撃が大きく、子どもや高齢者には不向き
- 施工費用が高め
ヘーベルハウスでは、水回りに適したタイル材を標準仕様として選択できるため、キッチンや洗面所などに採用することでメンテナンスの手間を減らすことが可能です。
ただし、寒冷地では冷たさがネックになるため、床暖房の導入も検討すると快適に過ごせます。
カーペットの特徴
カーペットは、防音性とクッション性に優れた床材で、主に寝室や子ども部屋に採用されることが多いです。
特に、防音性が求められる二世帯住宅や集合住宅においては、カーペットを活用することで生活音を軽減できます。
メリット
- 防音性が高く、足音や物音を抑えられる
- クッション性があり、転倒時の衝撃を軽減できる
- 冬場でも暖かく、冷えを防ぐ効果がある
デメリット
- 汚れやすく、掃除に手間がかかる
- ダニやホコリが溜まりやすく、定期的なクリーニングが必要
- 長期間使用すると、毛羽立ちやへたりが発生する
ヘーベルハウスでは、寝室や子ども部屋の防音対策としてカーペットを選択することができます。
ただし、掃除の頻度を増やす必要があるため、アレルギーを持つ方は注意が必要です。
どの床材を選ぶべきか?
床材の選択は、部屋の用途やライフスタイルによって最適なものを選ぶことが重要です。
以下の表に、それぞれの用途に応じたおすすめの床材をまとめました。
| 使用場所 | おすすめの床材 |
|---|---|
| リビング・ダイニング | フローリング(突板・挽板) |
| 玄関・キッチン | タイル |
| 寝室 | フローリングまたはカーペット |
| 子ども部屋 | カーペット |
| 水回り(洗面所・トイレ) | タイル |
ヘーベルハウスでは、各床材の特性を活かしながら、適切な組み合わせを提案することが可能です。
特に、リビングやダイニングはフローリング、水回りはタイル、寝室はカーペットといった使い分けをすることで、快適な住環境を実現できます。
また、冷えや防音対策として、床暖房の併用やカーペットとの組み合わせを検討するのも良い選択肢です。
家族構成やライフスタイルに合わせて、最適な床材を選ぶことで、長く快適に暮らせる住まいを実現できるでしょう。
ヘーベルハウスの床下メンテナンス費用はどれくらい?

ヘーベルハウスの床下メンテナンス費用は、一般的な木造住宅と比べるとやや高めに設定される傾向があります。
これは、ヘーベルハウスが採用しているALCコンクリート(軽量気泡コンクリート)や鉄骨構造が、木造住宅とは異なる専門的な技術を必要とするためです。
また、耐久性を重視した設計になっていることから、メンテナンスの頻度自体は少なくても、必要な場合の費用はしっかりかかる点を理解しておく必要があります。
床下のメンテナンス費用は、大きく分けて点検費用、補修費用、防湿・防蟻処理費用の3つのカテゴリーに分類できます。
1. 床下点検費用
ヘーベルハウスでは、定期点検サービスを提供しており、新築後の10年、15年、30年のタイミングで無料点検を受けることができます。
ただし、これらの点検は「基本的な劣化や異常がないかを確認する」ものであり、詳細な調査が必要な場合には追加費用が発生することがあります。
一般的な床下点検の相場は10,000円~30,000円程度ですが、ヘーベルハウスの場合、より詳細な検査を依頼する場合は50,000円以上かかることもあります。
特に、床下の給排水管やシロアリの侵入状況を確認するためにカメラ調査や専門業者の診断を依頼する場合は、費用が高くなることが予想されます。
2. 床下補修費用
ヘーベルハウスの床下は、基本的にALCコンクリートと鉄骨で構成されているため、木造住宅のように頻繁な補修は必要ありません。
しかし、給排水管の劣化、床の沈み込み、断熱材の劣化などが発生することがあります。
特に、床下の断熱材は、時間が経過すると劣化し、冷えやすくなる場合があります。
この場合、断熱材の交換を行うと1㎡あたり10,000円~15,000円の費用が発生します。
また、床の一部が沈み込んだり、補強が必要になった場合は、補修費用として50,000円~200,000円程度のコストがかかることもあります。
3. 防湿・防蟻処理費用
ヘーベルハウスの床下はシロアリ被害を受けにくい構造になっていますが、絶対に安全というわけではありません。
特に、給排水管の周辺や断熱材部分にはシロアリが侵入する可能性があるため、10~15年ごとに防蟻処理を行うことが推奨されています。
一般的な防蟻処理の相場は、1㎡あたり3,000円~5,000円です。
また、防湿対策として追加で床下の換気設備を設置する場合、100,000円~300,000円の費用が発生することもあります。
ヘーベルハウスは、通常の木造住宅と比べてメンテナンスの頻度は少ないですが、点検や補修が必要になった際にはやや高額になる可能性があるため、メンテナンス費用を事前に考慮した資金計画を立てることが重要です。
ヘーベルハウスの床下をより快適にするための工夫

ヘーベルハウスの床下は、耐久性や耐震性に優れた構造を持っていますが、快適な住環境を維持するためには、適切な対策や工夫が必要になります。
特に、「床下の温度調整」「防音対策」「防湿対策」などを考慮することで、より暮らしやすい空間を実現することが可能です。
1. 床下の温度調整対策
ヘーベルハウスの床下は、ALCコンクリートを使用しているため、一般的な木造住宅と比べると冷えやすいという特徴があります。
特に冬場は、床が冷たく感じることが多いため、以下のような対策を講じると良いでしょう。
-
床暖房の導入
ヘーベルハウスでは、オプションとして床暖房を採用することができます。
床全体を均一に温めることで、冬場の冷えを防ぎ、より快適に過ごせます。 -
カーペットやラグの活用
フローリングのままだと、直接床の冷たさを感じやすいため、カーペットやラグを敷くことで保温性を高めることができます。 -
高性能断熱材の追加設置
床下に断熱材「ネオマフォーム」を追加することで、外気の影響を受けにくくなり、冷暖房の効率が向上します。
2. 防音対策
ヘーベルハウスは耐震性の高い鉄骨構造を採用しているため、木造住宅に比べて「音が響きやすい」という特性があります。
特に床の足音や振動が下の階に響くことを防ぐためには、以下の対策を講じると効果的です。
-
防音フローリングの採用
床材を防音仕様のものに変更すると、生活音の伝わりを軽減することができます。 -
二重床構造の導入
オプションで二重床にすることで、遮音性が向上し、特に二世帯住宅や賃貸併用住宅の場合に効果的です。 -
カーペットを敷く
フローリングの上にカーペットや防音マットを敷くことで、足音を吸収し、静かな環境を保つことができます。
3. 防湿・換気対策
ヘーベルハウスの床下は、連続布基礎構造によって通気性が確保されていますが、湿気がこもりやすい地域では追加の換気対策を行うとより安心です。
-
床下換気システムの導入
床下の湿気を効率よく排出するため、換気システムを設置することでカビや腐食を防ぐことができます。 -
除湿機の使用
室内の湿度が高くなりやすい場合、除湿機を使って湿気をコントロールするのも一つの方法です。 -
防湿シートの追加設置
特に湿気が多い地域では、地面に防湿シートを敷くことで、湿気の上昇を抑えることができます。
このように、ヘーベルハウスの床下をより快適にするためには、温度管理、防音対策、防湿対策の3つのポイントを意識することが重要です。
建築時にこれらの対策を考慮しておくことで、より長く快適に暮らせる住まいを実現できます。
- ヘーベルハウスの床下はALCコンクリートを使用し、耐久性・耐震性・耐火性に優れている
- 連続布基礎を採用し、建物全体の荷重を分散させることで安定性を高めている
- 床下点検口を各部屋に設置し、メンテナンスしやすい構造になっている
- 床下の防湿対策はALCコンクリートと通気性の確保により、湿気がこもりにくい
- 床下浸水に強く、水が溜まりにくい構造になっている
- 高性能断熱材「ネオマフォーム」を使用し、断熱性能を向上させている
- 床材にはフローリング、タイル、カーペットなど多様な選択肢がある
- シロアリ被害を受けにくいが、防蟻処理や定期的な点検が推奨される
- 床下の冷えを軽減するために床暖房の導入が効果的である
- 重い家具を置く場合は、床の耐荷重や補強の検討が必要
- 防音対策として二重床構造や防音フローリングを導入することが可能
- 床下点検費用は10,000円~30,000円、補修費用は50,000円~200,000円程度かかる
- 床下換気システムを追加することで、より快適な環境を維持できる
- 防湿シートの使用は地域や地盤の状況によって追加対策が必要になる場合がある
- ヘーベルハウスの床下メンテナンスを定期的に行うことで、長期的に快適な住環境を維持できる

住宅展示場やオープンハウスに行くのは面倒だから、
自宅でゆっくり間取りと見積もりを比較したい…。
そんな時に便利に活用できるのが『タウンライフ家づくり』です。
気になるハウスメーカーや工務店を選び、希望する間取りや予算を入力するだけで、オリジナルの間取り&見積もりを無料で作成してもらえます。

憧れの大手ハウスメーカーがあなただけの間取りプランを無料で作ってくれます。
▼厳選ハウスメーカー1,170社以上と提携▼
▼オリジナル間取りプランの例▼
『タウンライン家づくり』がおすすめなのはこんな人↓
- あなただけの間取りプランと見積もりを無料で手に入れたい
- 営業マンの強引な勧誘が苦手・嫌い
- 自宅にいながら好みのハウスメーカーを選びたい





















